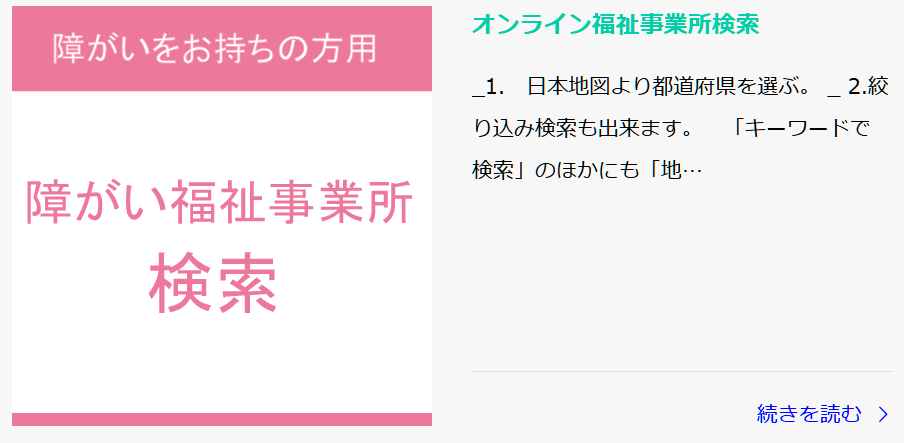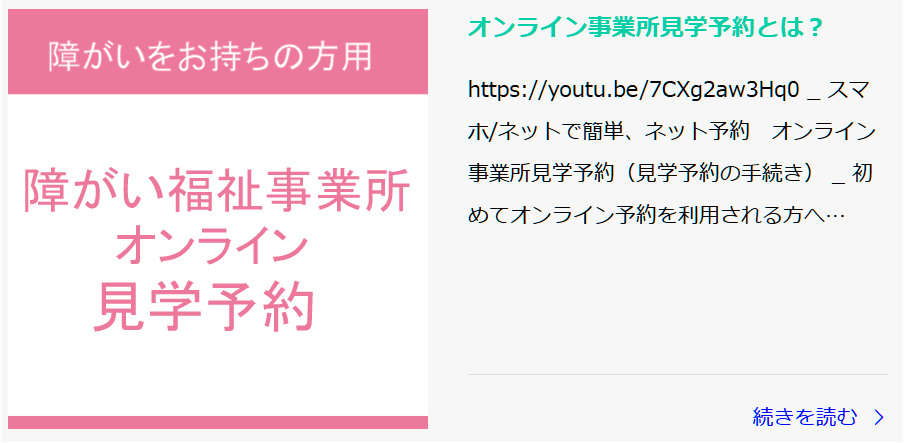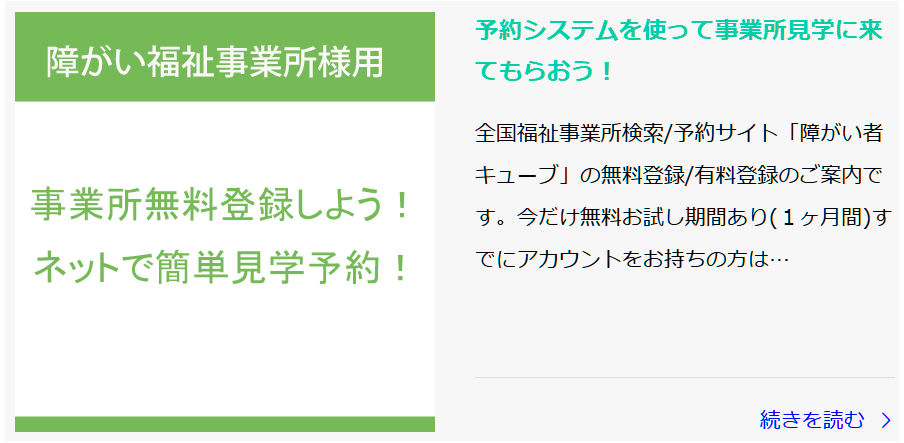・会議招集・情報共有の場の設定
YCCが参加機関を検討し、会議招集を行い、開催します。その際、何が課題であり、なぜ多機関連携が必要なのか、また、個別ケース会議のゴールをどこに置くのかを明確にする必要があります。本人や家族の希望がある場合、なるべく当事者も参加できるように配慮することも必要です。
会議調整に時間を要する場合は、まずは少ない関係者で情報共有を行うことも有効です。本人や家庭にとって心理的ハードルの低い支援機関から紹介したり、できるところから連携を始めることもできます。
・関係者によるヤングケアラーのニーズの把握・支援方針決定(会議開催等)
招集された関係者は会議に参加し、各専門性に基づきどうすれば本人や家族によって望ましい支援ができるか考えましょう。ヤングケアラーの支援を検討する際、できる限りヤングケアラーを含む家族の状況を正確に把握しておくことが重要です。家族関係や社会資源との関わりにも注目しましょう。YCCが収集した情報や、会議参加者がそれぞれ把握している本人や家庭の状況を基に、異なる視点や情報を共有することで多角的な支援が可能になります。
ポイント
● 長期目標や短期目標を決めましょう。
● 支援における役割分担を決めます。それぞれができることを出し合い、その家庭に最善な方法を考えます。
・支援計画作成
会議内容を基に、YCCが支援計画を作成します。
・支援のポイント
支援計画に基づき、各機関が実際に支援をしていきます。支援のポイントとして以下のような点があります。
福祉部門のサービスは、ケアを受ける家族へのサポートであることも多く、有効な支援ができれば間接的にヤングケアラーの支援につながります。既存のサービスを生かしたヤングケアラー支援について、福祉、介護、医療等各分野における国発出の各種通知・資料等も参照し、有効活用し支援していきましょう(下の表を参照)。
福祉サービス等の導入や追加をする場合は、それらの内容について、ヤングケアラーに対し、分かりやすく説明することも必要です
〇ヤングケアラー支援に関する国通知等
|
分野 |
内容・資料名 |
|
障害福祉 |
ヤングケアラーがいる家庭に対する計画相談支援の実施については、障害福祉サービス上の加算等の取扱いもあります。 |
|
高齢者福祉 |
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて、利用者に同居家族(ヤングケアラー含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではありません。 |
|
医療 |
令和4年度より、入退院支援加算1及び2の対象者にヤングケアラー及びその家族が追加されました。 |
● ヤングケアラー本人の援助希求力・レジリエンスの向上を支援する
ヤングケアラーの家庭は複合的な困難を抱えていることが多く、当事者の困り感やニーズが明確でなかったり、情報がなかったりし、なかなか適切に支援を頼ることが難しいという現状があります。「共感型支援」の中で気持ちを吐き出して頭の中を整理したり、様々な情報提供を受けたり、自分自身の試行錯誤を共有したりするプロセスの中で、自分自身が本当は何に困っているのか、そしてそれはどう伝えたら良いかを考える練習になり、いざ支援を求める際にもその経験が生かされ、正しく必要なリソースを頼れるようになっていく、そのための一連の支援をしていくことも大切です。
ケアそのものをゼロにするのが難しい場合には、適切に援助を頼りながら「withケア」の生活を送っていける力は非常に重要です。ピアサポートの民間団体等は、そのように意識しながら、寄り添いをしています。自治体・支援機関においても、そのような視点を持ちながら支援をしましょう。
・支援後の見守り、進行管理・モニタリングの重要性
課題解決型支援等で福祉サービス等が入ったあとも、ヤングケアラーは戸惑いや困難を感じることがあります(例:介護ヘルパーとのコミュニケーション等)。継続してヤングケアラーの様子を気にかけ、ヤングケアラーが日々感じる思いを受け止める人が身近にいることが大切です。各支援者が地域と連携をしながら、必要に応じて声かけをする、変化を感じ取った場合にはすぐにYCCに情報が集約される仕組みが望ましいでしょう。定期的に会議等を設け確認していくことも有効です。
こども特有の状況として、学校がある時期、長期休み期間で、必要な支援が変 わる可能性があります。また、進学、進路検討のタイミングで、支援が入っていても、将来的なケア役割を考えて希望する進路を諦めてしまう場合等があります。
一度支援が入っても、状況に応じ見直す必要がないか気にかけましょう。
見守り、進行管理・モニタリングのポイント
a.本人の成長・ライフステージ(進学等)
b.ケアを受けている家族の状況の変化(入退院・施設入所等)
c.それ以外の家族の状況の変化(出産、離婚等家族構成の変化等を含む)
の3要素が要因となり得ます。これらの変化があった際は、必要な支援が変わる可能性が高く、特に気にかけましょう。
(ケアが終わった後に、相談できる相手がいなくなり孤立する可能性もある)
(こどもにとっては、福祉サービス等の支援者とのやりとりがありがたい一方で難しさを感じていることもある)