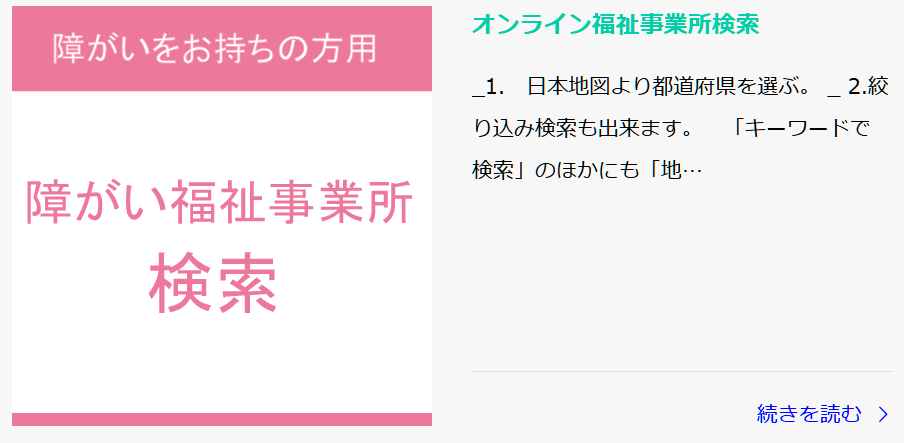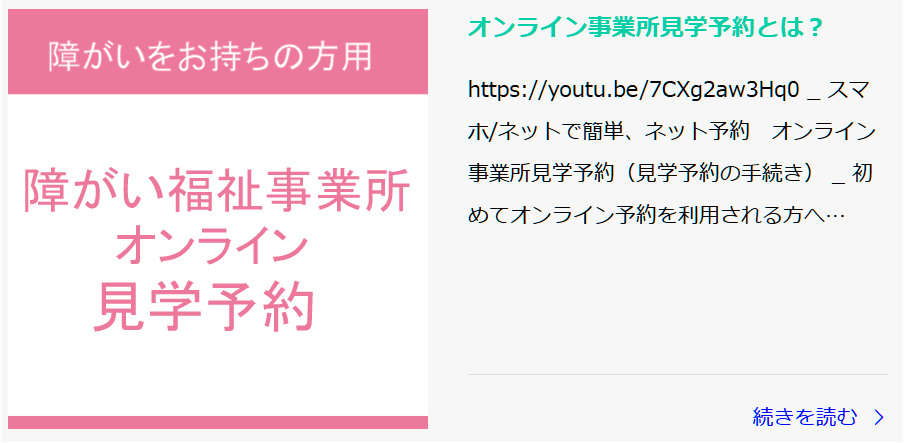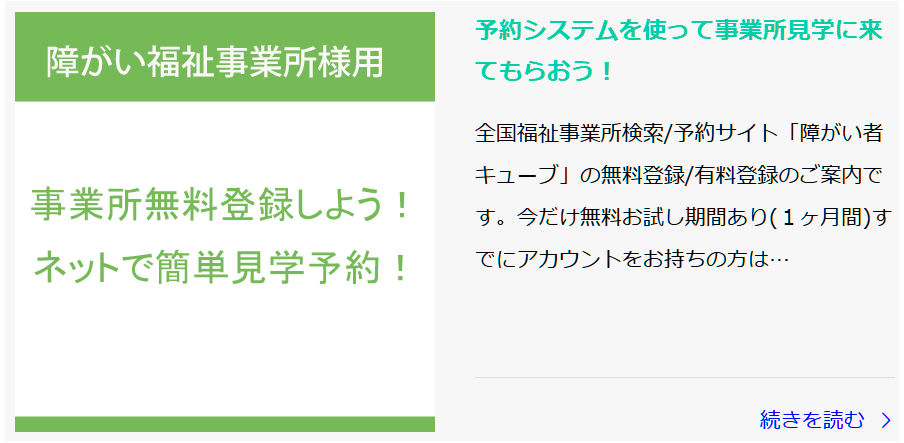視覚疾患について
視覚疾患について
主に遺伝的な要因によって視覚機能に異常をきたす疾患の総称で、代表的なものには網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、レーベル遺伝性視神経症などがあります。
これらはいずれも進行性で、病気が進むと視野欠損や視力低下などの症状をきたします。ですが同じ病気であっても、進行するスピードや現れる症状には極めて個人差があります。 これらの疾患は遺伝によるものであることから、最近の研究では、原因となる遺伝子の特定が徐々に進んできており、新しい治療法も研究・開発されてきています。
しかし今のところ進行を止めたり、視機能を回復するような治療法は見つかっていないのが現状です。 低下した視力を有効に活用するためには、眼鏡を正確に合わせるだけでなく、遮光眼鏡、ルーペ、PCやスマートフォンなどのIT機器や拡大読書器などの補助具をうまく活用することが大切です。眼科外来で自分の視力や視野を確認するとともに、学業や就労、職場での不自由さを軽減するために、ロービジョン外来や視覚障害者支援施設等でそれぞれの障害に合った支援を受けてください。
これらはいずれも進行性で、病気が進むと視野欠損や視力低下などの症状をきたします。ですが同じ病気であっても、進行するスピードや現れる症状には極めて個人差があります。 これらの疾患は遺伝によるものであることから、最近の研究では、原因となる遺伝子の特定が徐々に進んできており、新しい治療法も研究・開発されてきています。
しかし今のところ進行を止めたり、視機能を回復するような治療法は見つかっていないのが現状です。 低下した視力を有効に活用するためには、眼鏡を正確に合わせるだけでなく、遮光眼鏡、ルーペ、PCやスマートフォンなどのIT機器や拡大読書器などの補助具をうまく活用することが大切です。眼科外来で自分の視力や視野を確認するとともに、学業や就労、職場での不自由さを軽減するために、ロービジョン外来や視覚障害者支援施設等でそれぞれの障害に合った支援を受けてください。
主な疾患と特徴
 1.網膜色素変性症
1.網膜色素変性症
WHOによれば、世界中で推計2億5300万人、日本には約164万人の視覚障害者がいるといわれています。
このうち網膜色素変性症は、中途失明の原因の第2位であり、日本全国では現在、2万8千人の患者さんがいるともいわれています。視覚疾患の難病の中でこの疾患の次に数が多い黄斑ジストロフィーの患者数が約200人ですので、この網膜色素変性症の患者がいかに多いかがわかります。 網膜色素変性症は、目の内側にある網膜という部分に異常をきたす遺伝性、進行性の病気です。
網膜は光を神経の信号に変える働きをします。そしてこの信号は視神経から脳へ伝達され、私たちは光を感じることができるわけです。網膜には色々な細胞が存在していてそれぞれが大切な働きをしていますが、網膜色素変性症ではこの中の視細胞という細胞に障害が最初にみられます。視細胞は目に入ってきた光に最初に反応して光の刺激を神経の刺激、すなわち電気信号に変える働きを担当しています。視細胞には、大きく分けて2つの種類の細胞があります。ひとつは網膜の中心部以外に多く分布している杆体(かんたい)細胞で、この細胞は主に暗いところでの物の見え方や視野の広さなどに関係した働きをしています。もうひとつは錐体細胞で、これは網膜の中心部である黄斑と呼ばれるところに多く分布し、主に中心の視力や色覚などに関係しています。
網膜色素変性症ではこの二種類の細胞のうち杆体が主な障害となることが多く、このために暗いところで物が見えにくくなったり(夜盲)、視野が狭くなったりするような症状を最初に起こします。そして病気の進行とともに視力が低下していきます。ここで視力というのは、矯正視力(眼鏡レンズなどで、遠視、近視や乱視等を可能な限り補正して測定する視力)のことです。ちなみに、裸眼視力の変化は病気の進行や網膜の能力の変化の正確な目安にはならないと考えられています。
このうち網膜色素変性症は、中途失明の原因の第2位であり、日本全国では現在、2万8千人の患者さんがいるともいわれています。視覚疾患の難病の中でこの疾患の次に数が多い黄斑ジストロフィーの患者数が約200人ですので、この網膜色素変性症の患者がいかに多いかがわかります。 網膜色素変性症は、目の内側にある網膜という部分に異常をきたす遺伝性、進行性の病気です。
網膜は光を神経の信号に変える働きをします。そしてこの信号は視神経から脳へ伝達され、私たちは光を感じることができるわけです。網膜には色々な細胞が存在していてそれぞれが大切な働きをしていますが、網膜色素変性症ではこの中の視細胞という細胞に障害が最初にみられます。視細胞は目に入ってきた光に最初に反応して光の刺激を神経の刺激、すなわち電気信号に変える働きを担当しています。視細胞には、大きく分けて2つの種類の細胞があります。ひとつは網膜の中心部以外に多く分布している杆体(かんたい)細胞で、この細胞は主に暗いところでの物の見え方や視野の広さなどに関係した働きをしています。もうひとつは錐体細胞で、これは網膜の中心部である黄斑と呼ばれるところに多く分布し、主に中心の視力や色覚などに関係しています。
網膜色素変性症ではこの二種類の細胞のうち杆体が主な障害となることが多く、このために暗いところで物が見えにくくなったり(夜盲)、視野が狭くなったりするような症状を最初に起こします。そして病気の進行とともに視力が低下していきます。ここで視力というのは、矯正視力(眼鏡レンズなどで、遠視、近視や乱視等を可能な限り補正して測定する視力)のことです。ちなみに、裸眼視力の変化は病気の進行や網膜の能力の変化の正確な目安にはならないと考えられています。
この病気は視細胞や、視細胞に密着している網膜色素上皮細胞で働いている遺伝子の異常によって起こるとされています。以前は原因となる遺伝子がわかっているのは網膜色素変性症の患者さん全体のごく一部でしかなかったのですが、最近の研究で日本人に多い遺伝子の変化があきらかになって、解析の精度とスピードもアップしてきています。
現在までにわかっている原因遺伝子としては常染色体劣性網膜色素変性症ではEYS、杆体cGMP-フォスフォジエステラーゼαおよびβサブユニット、杆体サイクリックヌクレオチド感受性陽イオンチャンネル、網膜グアニルシクラーゼ、RPE65、細胞性レチニルアルデヒド結合蛋白質、アレスチン、アッシャリン(USH2)などの遺伝子が知られています。なかでもEYS遺伝子に異常が見つかる例が比較的多いことがわかっています。常染色体優性網膜色素変性症ではロドプシン、ペリフェリン(PRPH2・別名RDS)が主なものとされています。
X連鎖性網膜色素変性症では原因遺伝子として網膜色素変性症GTPase調節因子(RPGR)とRP2の2種類が同定されています。今後さらに原因となる遺伝子異常が同定される見込みです。遺伝子の変化をみてひとりひとりにあったカウンセリングや治療を目標として、効率のよい遺伝子診断法が研究されています。 このように網膜色素変性症といっても原因となる遺伝子異常は多くの種類があり、それぞれの遺伝子異常に対応した網膜色素変性症の型があるため症状も多彩です。
X連鎖性網膜色素変性症では原因遺伝子として網膜色素変性症GTPase調節因子(RPGR)とRP2の2種類が同定されています。今後さらに原因となる遺伝子異常が同定される見込みです。遺伝子の変化をみてひとりひとりにあったカウンセリングや治療を目標として、効率のよい遺伝子診断法が研究されています。 このように網膜色素変性症といっても原因となる遺伝子異常は多くの種類があり、それぞれの遺伝子異常に対応した網膜色素変性症の型があるため症状も多彩です。
最も一般的な初発症状は、暗いところでの見え方が悪くなること(夜盲)です。生活の環境によっては気がつきにくいことも多いようです。最初に、視野が狭くなっていること(視野狭窄)に気がつくこともあります。例えば、ひとにぶつかりやすくなったり、あるいは車の運転に支障がでるといったことが、気づくきっかけになります。視力の低下や色覚異常は、さらにあとから出てくるのが典型的です。しかし、コントラストの低い印刷物や罫線が読みづらいことを早くから自覚していることもあります。日常の生活環境でまぶしく感じる(羞明/しゅうめい)、あるいは全体が白っぽく感じることもあります。
この病気は原則として進行性ですが、症状の進行の速さには個人差がみられます。一般的には、視力低下、視野異常等の症状は発症後ゆっくりと進行していきます。ただし、数年で視力が極端に低下する場合もあれば、中高年以降まで読み書きができる程度の視力が残る場合もあります。また、さらに症状の組み合わせや順番にも個人差がみられ、最初に視力の低下や色覚異常で発見される場合もあり夜盲は後になる患者さんもいます。
また長い経過の後に字が読みにくい状態(矯正視力0.1以下)になる方は多いですが、暗黒になる方はむしろあまり多くありません。この個人差はこの病気の原因となっている遺伝子異常が非常に多彩であるため、ひとりひとりが異なった遺伝子異常であることに由来するのかもしれません。しかし、同じ家系の中で当然同じ遺伝子異常と考えられる患者さんでも、その進行度や重症度に差のある場合も判明してきましたので、まだわかっていない色々な要因によって病気の進行度や重症度が左右されている可能性があります。
また長い経過の後に字が読みにくい状態(矯正視力0.1以下)になる方は多いですが、暗黒になる方はむしろあまり多くありません。この個人差はこの病気の原因となっている遺伝子異常が非常に多彩であるため、ひとりひとりが異なった遺伝子異常であることに由来するのかもしれません。しかし、同じ家系の中で当然同じ遺伝子異常と考えられる患者さんでも、その進行度や重症度に差のある場合も判明してきましたので、まだわかっていない色々な要因によって病気の進行度や重症度が左右されている可能性があります。
したがって同じ病名であるからといって同じ症状や重症度、進行度を示すわけではないことを十分に理解して下さい。その上で自分の病気の進行度や重症度を専門医に診断してもらうとよいでしょう。進行度をみるためには当然1回の診察だけでは診断は不可能です。定期的に何回か診察や検査を受けて初めてその人の進行度を予想することができます。近年、通常の眼底検査や眼底カメラ撮影による検査の他に、通常の検査では観察できない網膜色素上皮の変化をみる自発蛍光撮影、網膜の断層撮影が可能な光干渉断層撮影計(OCT)が普及してきました。これらは比較的、患者さんが負担を感じることが少ない検査で、病気の診断の精度を上げるだけでなく、進み具合などを調べるのに有用であることが報告されています。
また、ほかの眼の病気も合併していることもありますが、白内障は比較的多くみられます。白内障は水晶体(レンズ)が濁ってくる病気の総称で、高齢になると増える病気ですが、網膜色素変性症の一部の患者さんでは、より若い時からおこることもあります。水晶体の濁りのため光がまっすぐに目に入らないため、まぶしくなったり、にじんでみえたりします。
網膜色素変性症があっても、手術的に水晶体の濁りを取り除いて代わりになるレンズ(眼内レンズ)に置き換えることは通常は可能です。他に目に病気がないかたにくらべて、眼内レンズの位置が変化する、後発白内障になりやすいなどの合併症はおこるリスクがある程度は高くなりますが、多くは対処(追加の治療)が可能です。手術後の見え方を予想することが困難なこともあるので、手術により得るものとリスクとをよく検討したうえで方針を決めることが大切です。
網膜色素変性症があっても、手術的に水晶体の濁りを取り除いて代わりになるレンズ(眼内レンズ)に置き換えることは通常は可能です。他に目に病気がないかたにくらべて、眼内レンズの位置が変化する、後発白内障になりやすいなどの合併症はおこるリスクがある程度は高くなりますが、多くは対処(追加の治療)が可能です。手術後の見え方を予想することが困難なこともあるので、手術により得るものとリスクとをよく検討したうえで方針を決めることが大切です。
この病気には現在のところ、網膜の機能をもとの状態にもどしたり、確実に進行を止める確立された治療法はありません。対症的な方法として、遮光眼鏡(通常のサングラスとは異なるレンズ)の使用、ヘレニエン製剤(βカロテンの一種)内服、ビタミンA内服、循環改善薬による治療、低視力者用に開発された各種補助器具の使用などが行われています。遮光眼鏡は明るいところから急に暗いところに入ったときに感じる暗順応障害に対して有効であるほか、物のコントラストをより鮮明にしたり、また明るいところで感じる眩しさを軽減させたりします。
ビタミンAはアメリカ合衆国での研究で網膜色素変性症の進行を遅らせる働きがあることが報告されていますが、すべての患者さんにはあてはまらない可能性があります。通常の量以上に内服して蓄積すると副作用を起こすこともあります。また、循環改善薬による治療も必ずしも全員に対して有効であるわけではないのですが、使用により視野が少し広がる、明るくなる患者さんがみられます。
確実な治療法がない現在、最も重要なことは以下の通りです。
①眼科疾患の中でも進行の遅い疾患ですので、視力視野の良いうちから慌てないこと
②矯正視力や視野結果を理解して自分の進行速度を把握すること
③進行速度から予測される将来に向けて準備をすること
④視機能が低下してきても各種補助器具を用いて残存する視力視野を有効に使い生活を工夫することです。補助具のうち拡大読書器などを使えば、かなり視力が低下してからも字を読んだり書いたりすることが可能です。コンピューターの音声ソフトによるインターネットやメールもうまく活用できたりします。
確実な治療法がない現在、最も重要なことは以下の通りです。
①眼科疾患の中でも進行の遅い疾患ですので、視力視野の良いうちから慌てないこと
②矯正視力や視野結果を理解して自分の進行速度を把握すること
③進行速度から予測される将来に向けて準備をすること
④視機能が低下してきても各種補助器具を用いて残存する視力視野を有効に使い生活を工夫することです。補助具のうち拡大読書器などを使えば、かなり視力が低下してからも字を読んだり書いたりすることが可能です。コンピューターの音声ソフトによるインターネットやメールもうまく活用できたりします。
将来期待される治療法として、遺伝子治療、網膜移植、人工網膜さらに代替レチノイドなどの研究が行われています。これらの治療法はまだ実際に誰に対しても行える治療法とはなっていませんが、研究段階ですがその成果は次第に上がってきています。2007年から、アメリカ合衆国とイギリスで、RPE65遺伝子の変化でおこる網膜色素変性症の遺伝子治療が試みられています。子供のころから発症する重症な網膜色素変性症ですが、安全性の確認とその効果について検討されていて、まだ短期間の観察ですが、有効性が期待できそうな報告がされています。
別の研究グループは、やはりRPE65遺伝子やビタミンAを網膜内で利用に関連する遺伝子の異常でおこる網膜色素変性症をもつ患者さんに「代替レチノイド」を内服してもらう治療研究が行なわれています。
別の研究グループは、やはりRPE65遺伝子やビタミンAを網膜内で利用に関連する遺伝子の異常でおこる網膜色素変性症をもつ患者さんに「代替レチノイド」を内服してもらう治療研究が行なわれています。
現在のところ、重い副作用もなく今後の治療応用が期待されています。我が国ではこれらの治療は始められていませんが、新しい治療への動きは着実に始まっています。日本では、網膜の視細胞をできるだけ長生きさせるように、神経保護因子を目のなかで多く作らせるような遺伝子を補う研究が始まっていて、現在安全性を確認する臨床試験が行われています。人工網膜については、最近我が国で安全性と効果を確かめる試験が行なわれ、臨床応用へと進む可能性が高くなっています。
また、網膜色素上皮細胞の萎縮に対して再生医療を応用する試みも始まっていて、現在、iPS細胞を用いた治療を加齢黄斑変性の患者さんに応用する研究が行われていますが、将来網膜色素変性症にも応用できる可能性がでてきました。
また、網膜色素上皮細胞の萎縮に対して再生医療を応用する試みも始まっていて、現在、iPS細胞を用いた治療を加齢黄斑変性の患者さんに応用する研究が行われていますが、将来網膜色素変性症にも応用できる可能性がでてきました。
 2.黄斑ジストロフィー
2.黄斑ジストロフィー
黄斑ジストロフィーとは、遺伝学的な原因によって網膜の黄斑部がゆっくりと障害が進み、両眼の視力低下や視野異常を生じる病気の総称です。黄斑部は非常に繊細な構造をしているために、多くの疾患が生じやすい部位でもあります。
障害される視細胞の種類や関連する遺伝子によって、スタルガルト病、錐体杆体ジストロフィー、卵黄状黄斑ジストロフィー(ベスト病)、X連鎖性若年網膜分離症、オカルト黄斑ジストロフィー、中心性輪紋状網脈絡膜萎縮など、いくつかの代表疾患に分類されています。
特に、スタルガルト病、卵黄状黄斑ジストロフィー(ベスト病)、錐体杆体ジストロフィー、オカルト黄斑ジストロフィーなどでは、発症に関与する遺伝子が特定されています。
特に、スタルガルト病、卵黄状黄斑ジストロフィー(ベスト病)、錐体杆体ジストロフィー、オカルト黄斑ジストロフィーなどでは、発症に関与する遺伝子が特定されています。
これらの常染色体優性遺伝の疾患では子供に遺伝する可能性があります。ただしスタルガルト病のように常染色体劣性遺伝の疾患では、通常は子供に遺伝することはありません。またX連鎖性若年網膜分離症の場合は、子供が男性の場合は発症しませんが、子供が女性の場合はその女性の男児に発症する可能性があります。
また、上記の分類に入らない黄斑ジストロフィーや分類不能の黄斑ジストロフィーも多く見られます。 このような分類不能の黄斑ジストロフィーも、代表疾患と同様に厚生労働省の難病指定を受けることができます。
この疾患には性質の異なる幾つかの疾患が含まれるため、タイプによって、また個人によっても症状は異なります。一般的には、視力を保つために重要な黄斑部が障害されるため、視力低下(眼鏡をかけても視力が出ない)、中心視野異常(見ようと思う中心部がぼやける)等の症状が両眼にゆっくりと出現します。
また、色覚異常や羞明(まぶしく感じる)等の症状も多く見られます。さらに、錐体杆体ジストロフィーやスタルガルト病のうち重症のタイプでは、視野障害が視界の周辺部まで広がることがあります。
また、色覚異常や羞明(まぶしく感じる)等の症状も多く見られます。さらに、錐体杆体ジストロフィーやスタルガルト病のうち重症のタイプでは、視野障害が視界の周辺部まで広がることがあります。
ただし前述の網膜色素変性症と同じく、この疾患も症状やその経過には個人差があり、人によって、あっという間にほとんど失明してしまう人もいれば、ある程度年齢を重ねるまで健康な眼を持ち続ける人もいます。また、一般的に発症時期が若年であるほど症状は重く、遅いほど最終的な障害は軽度であることが多いと考えられています。
網膜はもともと光(とくに紫外線)に弱い組織です。日常生活で長時間日差しの強いところに出る場合は、サングラス、つばの広い帽子などで目を守ることをお勧めします。
また、他の遺伝性の網膜疾患にも言えることですが、大病院の眼科外来などで正確な視力や視野を測った上で、視覚障害者用補助用具の斡旋や、視覚特別支援学校での点字の習得、視覚障害者用IT機器の学習など、障害の進行度合いに合わせて、各種視覚障害者支援機関などの支援を活用することが大切です。
また、他の遺伝性の網膜疾患にも言えることですが、大病院の眼科外来などで正確な視力や視野を測った上で、視覚障害者用補助用具の斡旋や、視覚特別支援学校での点字の習得、視覚障害者用IT機器の学習など、障害の進行度合いに合わせて、各種視覚障害者支援機関などの支援を活用することが大切です。
最後に、他の網膜の遺伝病のなかには、すでに遺伝子治療や薬物治療等が試験的に開始されている疾患もありますが、現在のところ、この疾患を根本的に治療する方法は見つかっていません。ですが医学は日々目覚ましい進歩を遂げていますので、将来的には、今後の研究の進展によりこの病気を根本的に治す方法が見つかる可能性もあります。
 3.レーベル遺伝性視神経症(レーベル病)
3.レーベル遺伝性視神経症(レーベル病)
細胞のなかでエネルギー産生を行うミトコンドリアという器官の遺伝子の異常により、網膜の一部の細胞に選択的な障害が起こる病気です。
ミトコンドリア遺伝子は原則として、すべて母親から受け継ぎます。従って母親から子に遺伝し、父親からは遺伝しないと考えられています。発症者は男性に多いのですが、男性患者の子孫には病気は受け継がれません。
この疾患は10〜30歳代に発症の大きなピークがあり、40歳代前後にもう一つのピークがあります。 発症すると数週間から数ヶ月の間に、両眼の視力低下、中心部の視野欠損が起こります。
この疾患は10〜30歳代に発症の大きなピークがあり、40歳代前後にもう一つのピークがあります。 発症すると数週間から数ヶ月の間に、両眼の視力低下、中心部の視野欠損が起こります。
前述の遺伝子変異に加えて何らかの発症要因が加わったときに発症します。酸化ストレスや喫煙が発症と進行に関連していることが報告されているほか、薬剤やホルモンなどとの関連も予測されていますが、その他のことはまだよく分かっていません。
片眼の視力低下と中心部の視野欠損から始まり、数週間から数ヶ月の間にもう片眼にも同じ症状が起こります。しかし完全に失明することは非常にまれで、また一部の症例では、視力が部分的ないしおおむね元通りに改善することもあります。
片眼の視力低下と中心部の視野欠損から始まり、数週間から数ヶ月の間にもう片眼にも同じ症状が起こります。しかし完全に失明することは非常にまれで、また一部の症例では、視力が部分的ないしおおむね元通りに改善することもあります。
治療法としては現在、コエンザイムQ10の誘導体であるイデベノンの有効性が示されつつあります。研究では、イデベノンはミトコンドリアのエネルギー産生を助け、網膜の細胞を細胞死から守る働きがあることが分かっています。実際の患者の方で有効かどうかは、内外で調査が進んでいるところです。
この他、コエンザイムQ10、ビタミンC、ビタミンB12の内服や、眼底の血流改善を目的とした点眼薬・内服薬を用いることもあります。また海外では治験として、ミトコンドリア遺伝子の遺伝子治療も行われています。
日常生活では、喫煙が発症と進行のリスクになることが証明されていますので、禁煙が重要です。
この他、コエンザイムQ10、ビタミンC、ビタミンB12の内服や、眼底の血流改善を目的とした点眼薬・内服薬を用いることもあります。また海外では治験として、ミトコンドリア遺伝子の遺伝子治療も行われています。
日常生活では、喫煙が発症と進行のリスクになることが証明されていますので、禁煙が重要です。
 ・Q&A
・Q&A
A1 遺伝子異常による眼疾患では、症状の違いや個人差はありますが、そのほとんどが進行性です。最初は他の人と同じように見えていますが、徐々に視力が低下したり視野が欠けたりします。そしてそれに伴って、それまで出来ていたことがだんだんと出来なくなる、あるいは難しくなっていきます。
視力低下によって物が見えにくくなるのはもちろん、視野欠損によって周りにある物を探すこともままならなくなります。
また障害需要の面では、先天性の視覚障害とは異なり、進行性の視覚疾患ではだんだんと見えなくなるため、自分がこれからだんだん見えなくなるという恐怖が最初におこり、次に見えなくなることへの不安が付きまといます。そして自分が視覚障害者になるということは、精神的にはもちろん、身体的にもなかなか受け入れがたいものです。
将来見えなくなることを見越して、点字学習やIT機器の活用など、視覚障害者の生活に慣れておく必要もあるでしょう。その過程で、自分はまだ見えるのになんでこんなことをしているのだろうという、心の葛藤もあるでしょう。 さらに長年見えていた感覚は体に染みついているため、見えないということに体が慣れるのにもなかなか時間がかかります。自分が思っている見え方と実際の見え方にギャップが生じるのです。
つまり、自分は見えているつもりで動作をするけれども、実際は思っているほど見えていないので動作がしにくいといったような状況になります。例を挙げると、パソコンを使用する際、見えている人は画面の文字や画像を見て、マウスを使って操作をしますが、見えなくなると画面は見ないしマウスも使用しません。その代わりに、画面の文字情報を音声で読み上げる機能(スクリーンリーダー)を耳で聞いて、キーボードを使ってすべての操作を行います。つまり、見えていた時の感覚で画面を見てマウスを動かそうとしますが、実際は見えないのでマウスカーソルがどこにあるのかもわかりません。
他に具体的に苦労することとしては、比較的見えている時に一般企業に障害者枠で就職し、企業側の配慮もあって順調に仕事をしていたけれども、その後徐々に視力が低下したため、視力必須の企業では仕事は続けられず、止むを得ず退職をした例もあります。
またこれは視覚障害者全体にも言えることですが、見た目ではどの程度見えているのか、見えていないのかということが、なかなか理解されにくく、誤解を受けるということもあります。例えば弱視の場合、その見え方はまさに千差万別です。一般の活字を拡大して文字を読む人も、その見えやすい拡大倍率は人によって異なります。他にも白黒反転すると見える人や明るいところで見えやすくなる人など、見え方は十人十色です。さらに、普段白杖を使って歩いている人が、スマートフォンを使っているということを知っている人はまだ多くはありません。このようなことから、本当は見えているのではないかなど、まだまだ偏見や誤解が存在することも事実です。
視力低下によって物が見えにくくなるのはもちろん、視野欠損によって周りにある物を探すこともままならなくなります。
また障害需要の面では、先天性の視覚障害とは異なり、進行性の視覚疾患ではだんだんと見えなくなるため、自分がこれからだんだん見えなくなるという恐怖が最初におこり、次に見えなくなることへの不安が付きまといます。そして自分が視覚障害者になるということは、精神的にはもちろん、身体的にもなかなか受け入れがたいものです。
将来見えなくなることを見越して、点字学習やIT機器の活用など、視覚障害者の生活に慣れておく必要もあるでしょう。その過程で、自分はまだ見えるのになんでこんなことをしているのだろうという、心の葛藤もあるでしょう。 さらに長年見えていた感覚は体に染みついているため、見えないということに体が慣れるのにもなかなか時間がかかります。自分が思っている見え方と実際の見え方にギャップが生じるのです。
つまり、自分は見えているつもりで動作をするけれども、実際は思っているほど見えていないので動作がしにくいといったような状況になります。例を挙げると、パソコンを使用する際、見えている人は画面の文字や画像を見て、マウスを使って操作をしますが、見えなくなると画面は見ないしマウスも使用しません。その代わりに、画面の文字情報を音声で読み上げる機能(スクリーンリーダー)を耳で聞いて、キーボードを使ってすべての操作を行います。つまり、見えていた時の感覚で画面を見てマウスを動かそうとしますが、実際は見えないのでマウスカーソルがどこにあるのかもわかりません。
他に具体的に苦労することとしては、比較的見えている時に一般企業に障害者枠で就職し、企業側の配慮もあって順調に仕事をしていたけれども、その後徐々に視力が低下したため、視力必須の企業では仕事は続けられず、止むを得ず退職をした例もあります。
またこれは視覚障害者全体にも言えることですが、見た目ではどの程度見えているのか、見えていないのかということが、なかなか理解されにくく、誤解を受けるということもあります。例えば弱視の場合、その見え方はまさに千差万別です。一般の活字を拡大して文字を読む人も、その見えやすい拡大倍率は人によって異なります。他にも白黒反転すると見える人や明るいところで見えやすくなる人など、見え方は十人十色です。さらに、普段白杖を使って歩いている人が、スマートフォンを使っているということを知っている人はまだ多くはありません。このようなことから、本当は見えているのではないかなど、まだまだ偏見や誤解が存在することも事実です。
A2 進行性の眼疾患は視野の欠損や視力の低下度合いに応じて工夫すべきことも変わってきます。例えば、視力はある程度残っていても周辺視野が欠損している場合、周囲の状況を目視することが困難になってきます。その場合、外出した際などに周囲の状況が分かりにくく、信号の場所を探すことも難しくなります。そのようなときは、スマートフォンで景色を写真に収め、それを拡大機能を使って信号の場所を確認します。
このように今や誰もが使っている最新のIT機器には、使い方次第で障害を克服し生きやすくする工夫が詰まっています。 他にも、一般の活字を拡大しても読むことができないくらい視力が衰えたとき、以前なら他の誰かに読んでもらうしか選択肢がありませんでした。しかし最近では、書類を専用のカメラで撮影し、そこに書かれている文字を機械が解析することで、書類の文字を声で読み上げる視覚障害者用の機械も登場してきています。 IT技術の進歩は、今や目覚ましいものがあります。そしてそれは大いに、障害を持つ人の助けとなっています。このIT技術を使いこなし生活を豊かにすることも、立派な工夫の一つと言えるでしょう。
このように今や誰もが使っている最新のIT機器には、使い方次第で障害を克服し生きやすくする工夫が詰まっています。 他にも、一般の活字を拡大しても読むことができないくらい視力が衰えたとき、以前なら他の誰かに読んでもらうしか選択肢がありませんでした。しかし最近では、書類を専用のカメラで撮影し、そこに書かれている文字を機械が解析することで、書類の文字を声で読み上げる視覚障害者用の機械も登場してきています。 IT技術の進歩は、今や目覚ましいものがあります。そしてそれは大いに、障害を持つ人の助けとなっています。このIT技術を使いこなし生活を豊かにすることも、立派な工夫の一つと言えるでしょう。
A3 視覚障害者は目でものを見ることができない分、当然、ほかの感覚、特に耳を使って周囲の情報を把握します。娯楽に関しても、耳を使って楽しめるものが多くあります。
最も代表的なものがラジオです。ラジオ番組はすべての情報を音で伝えます。そのため、晴眼者よりも聴覚が優れ、また想像力が豊かな視覚障害者は、ラジオから聞こえる音から状況や感情など、あらゆることを感じ取ります。特にわかりやすいのが野球などのスポーツ中継です。ラジオのスポーツ中継では、実況や解説のみでプレイヤーの動きを伝えます。そのため、ルールなど、そのスポーツについてのある程度の知識さえあれば音のみですべての情報を把握することができるのです。ですから視覚障害者にとってラジオは最適な娯楽の一つと言えます。
また読書も、視覚障害者にとって身近な娯楽の一つです。晴眼者が使用する文字(活字)を点字に訳す点訳ボランティアが全国にたくさんおられ、その方たちが活字の本などを点訳してくださるおかげで、視覚障害者も文学に親しむことができます。 問題点としては、読みたい本がその時すぐに読めるとは限らないということです。点訳ボランティアの方たちが日々、人気の本などを点訳してくださってはいますが、点訳という作業は途方もない時間と労力を要します。それに、そもそも点字を習得するのに時間がかかるため、ボランティアの数もなかなか増えません。
そこで点訳に代わり近年新たに増えつつあるのが音訳です。音訳はその名の通り本を朗読しそれを録音することです。音訳であれば特別な知識や作業の必要がなく、より早く、効率的に本を届けることができます。それに、視覚障害者でも点字を習得している人は、実のところ多くはありません。そういった意味でも視覚障害者にとって朗読は最適な読書の手段といえるかもしれません。 他にもテレビ鑑賞も、視覚障害者の立派な娯楽の一つです。見えないのにどうやってテレビを見るのかと不思議に思う方もいるかもしれませんが、見えない分、耳から入ってくる情報を使って情景や登場人物の姿、感情などをも想像し補うのです。その想像力で映画やドラマ、ドキュメンタリー番組など、たいていの番組は見ることができます。 ですが想像力にも限界があるのも事実です。そのために、最近では情景や人物の動作などを開設する音声ガイドがついた番組が徐々に増えてきています。いかに想像力が優れているとはいえ、音声ガイドがあるのとないのとでは雲泥の差があります。音声ガイドの開設は、景色の美しさや人物の細かな行動までをも端的に解説してくれます。そのおかげで、視覚障害があっても目の見える晴眼者と一緒に映画などを鑑賞し、同じタイミングで笑ったり泣いたりすることができるのです。
他の娯楽としては、視覚障害者も楽しめるように作られたトランプやマージャン、囲碁や将棋やオセロなどの各種のボードゲーム、そして視覚障害者用に作られたものや晴眼者が楽しめるものなども含めた各種のテレビゲームなども、ちょっとした工夫と練習によって遊ぶことができます。
また読書も、視覚障害者にとって身近な娯楽の一つです。晴眼者が使用する文字(活字)を点字に訳す点訳ボランティアが全国にたくさんおられ、その方たちが活字の本などを点訳してくださるおかげで、視覚障害者も文学に親しむことができます。 問題点としては、読みたい本がその時すぐに読めるとは限らないということです。点訳ボランティアの方たちが日々、人気の本などを点訳してくださってはいますが、点訳という作業は途方もない時間と労力を要します。それに、そもそも点字を習得するのに時間がかかるため、ボランティアの数もなかなか増えません。
そこで点訳に代わり近年新たに増えつつあるのが音訳です。音訳はその名の通り本を朗読しそれを録音することです。音訳であれば特別な知識や作業の必要がなく、より早く、効率的に本を届けることができます。それに、視覚障害者でも点字を習得している人は、実のところ多くはありません。そういった意味でも視覚障害者にとって朗読は最適な読書の手段といえるかもしれません。 他にもテレビ鑑賞も、視覚障害者の立派な娯楽の一つです。見えないのにどうやってテレビを見るのかと不思議に思う方もいるかもしれませんが、見えない分、耳から入ってくる情報を使って情景や登場人物の姿、感情などをも想像し補うのです。その想像力で映画やドラマ、ドキュメンタリー番組など、たいていの番組は見ることができます。 ですが想像力にも限界があるのも事実です。そのために、最近では情景や人物の動作などを開設する音声ガイドがついた番組が徐々に増えてきています。いかに想像力が優れているとはいえ、音声ガイドがあるのとないのとでは雲泥の差があります。音声ガイドの開設は、景色の美しさや人物の細かな行動までをも端的に解説してくれます。そのおかげで、視覚障害があっても目の見える晴眼者と一緒に映画などを鑑賞し、同じタイミングで笑ったり泣いたりすることができるのです。
他の娯楽としては、視覚障害者も楽しめるように作られたトランプやマージャン、囲碁や将棋やオセロなどの各種のボードゲーム、そして視覚障害者用に作られたものや晴眼者が楽しめるものなども含めた各種のテレビゲームなども、ちょっとした工夫と練習によって遊ぶことができます。