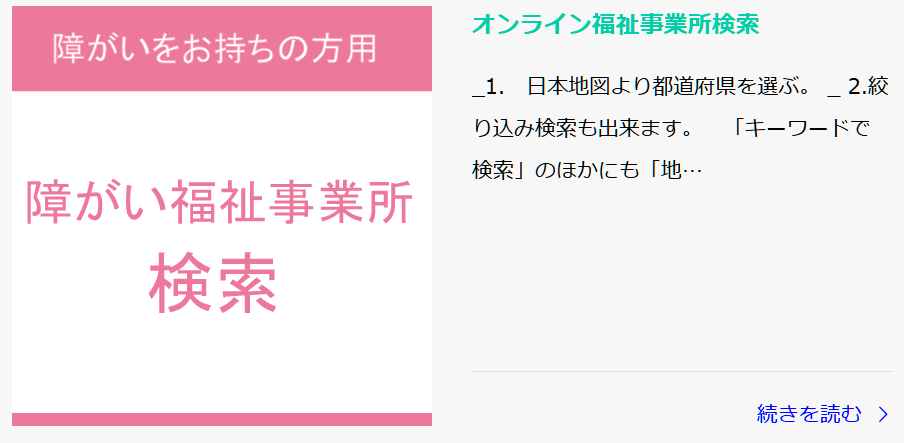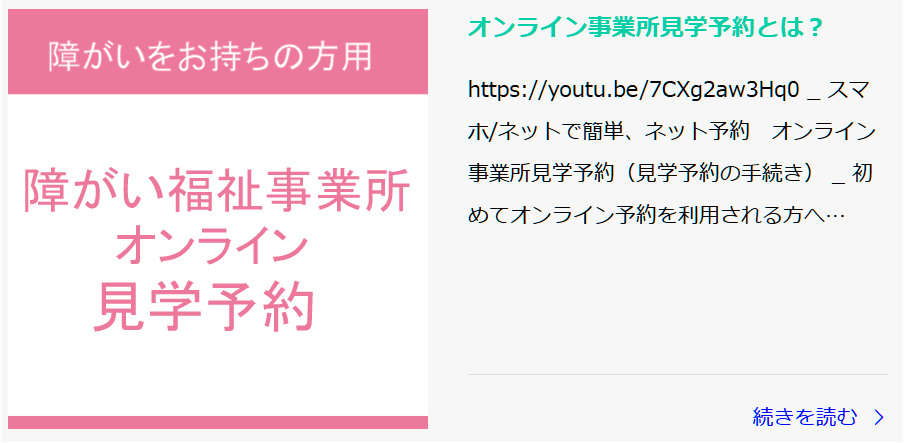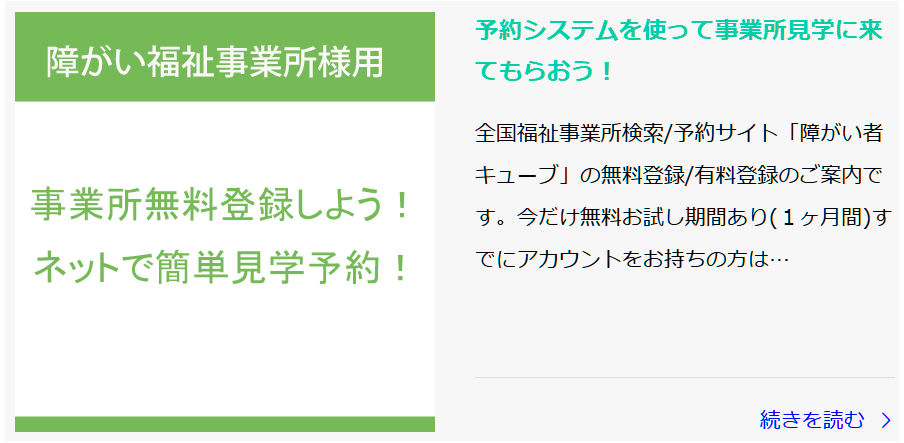目次
・ 障害を理解することを考えるために
障害者雇用の考えを進めてゆくと、自ずと障害を理解するために広く社会における障害者に対する現状や知識に興味を持つようになります。特に身近に障害者がいない環境で過ごしてきた社員にとって、いきなり障害者と一緒に仕事をするとなると、先入観や思い込みから障害のある社員と向き合いことになります。それはあまり良い結果を生まないことは、多くの事例が述べていることです。そこで、障害を理解するとは何かを「理解する」という観点から考察した山﨑裕子さんの論文「障害を『理解する』とは何か? 生き方の問題として問い直し」を読むことにします。
山﨑裕子さんは、当時法政大学のキャリアデザイン学部キャリアデザイン学科4年、「障害を 『理解する』 とは何か? 生き方の問題としての問い直し」は、第29回法政大学懸賞論文で優秀賞を受賞されました。
・ 山﨑論文の概要について
山﨑さんの論文の概要は「はじめに」に記されているように以下の通りです。
「障害がある」というのはどういうことだろうか? 「障害は個性」という時、そこにはどういう障害観が隠されているのだろうか? 「障害者」に対するとき、「健常者」と言われる人々は「受け入れる」側なのだろうか? 「『理解』が大切だ」という時、誰にとって大切なことなのか? 「理解」していることは何に基づいた「理解」なのか? この論文では、こうした疑問を明らかにします。そのために、障害に関わることから、障害に限らない、決定的に異なる他者との共存についての考察を重ねていきます。特に教育の場で急速に浸透している「発達障害をもつこども」を「理解」し、「支援」しようという動きにおいて、はたしてそれは本当にこどものためなのか? という疑問の解決と、現場の考察を今の時点で明確にすることを本論文の目的としています。
第1章では、障害観の転換について障害をもったひとを取り巻く社会の変容や、WHOの障害観の変化、障害児教育理念の歴史について述べています。
第2章では、「障害は個性か」という疑問に、障害は個性ではなく所属であるという見方から、特に教育の場で差異を「個性」としてしまうことの安易さを述べています。また、学校での「みんなちがって、みんないい」という言葉は強者の理論であることを述べ、さらに、時代の要請で「特別支援」されるという視点について触れています。
第3章では、特別支援教育で行なおうとしている「障害への理解と対応」が「診断」というラベリングの延長線上にあることについて述べています。
第4章では、今まで考察してきたことを、障害の有無に関わらない、人間の本質的な「他者との共存」という問題として捉えなおし、その上で、他者を「理解する」ことの限界について述べています。最後に、生きているということは、生かされていることでもあり、その視点から考えると、これまで「障害」の問題として語られてきたことが、実際には、社会の中で生きる「人として」、個人の「生き方」の問題として問い直すことができることを明らかにしています。
以下、論文の内容を損なうことなく、小見出しをつけ文中の引用をなるべく廃し、文意を損なわずに切り詰めて要点を明確にして読めるようにしました。
・ 第1章 障害観の転換の時代
1-1 障害観の転換
1-2 「本人主体」 の障害観
1-3 障害児教育理念の歴史
・ 第2章 障害は個性か?
2-1 「障害は個性」 か?
2-2 学校における異質性の捉え方
2-3 「特別支援」 される時代
・ 第3章 パターナリズムと偏見、差別
3-1 「診断」というラベリング
3-2 障害とアイデンティティ
・ 第4章 他者との共存とはどういうことか?
4-1 「理解する」ことの限界
4-2 「寛容であること」の問題
4-3 「生きる」ということ
・ おわりに
私は、二項対立の思想から脱することで、共生の実現に近づくことを、前述した。差異や偏りを他者が意図的になくすことではなく、日常の中で、受け容れていくことは、人を人として尊重するということである。
「障害」や「違い」以上に、人間としての尊厳を大切にしていかなくてはならない。それが、豊かに生きるということである。
「障害」をひとくくりに見ることで、個人の個別性への鈍感さが増すため、「障害」という枠組みで個人を語ることの安易さを明確にしてきた。特別支援教育での「障害への理解と対応」の批判を行ったが、それは不必要ということではない。過剰にし、なおかつそれを「いいこと」と信じたとき、それは本人のためではない、ということを主張したのである。
以上、山﨑裕子さんは、当時法政大学のキャリアデザイン学部キャリアデザイン学科4年、「障害を 『理解する』 とは何か? 生き方の問題としての問い直し」の要点を絞ったものです。
みなさんはこの文章を読んでどんなことを思われたでしょうか? 後半の教育について議論は、あまり関係ないと思う向きも解らなくはありませんが、文中にもあるように「こどもはこどものまま」ではありません。みなさんの隣にいる障害を持った働く仲間も、以前はこのような環境の中で育ってきたのです。また障害者雇用が当たり前となりつつある中で、教師や専門家のように接してしまわないとも限りません。
障害はあくまでも属性であり、個性ではありません。障害を理解するということが、個性を理解することにはつながらないことは、この論文でも解ることです。ならば私たちは、何を理解しようとしているのでしょうか。障害者の世界に不案内な者が、障害者の歴史や教育の実態を知ることは大切なことです。そして理解するということがわたしたちの暮らす世界にとってどういうことか、この論文は多くの示唆を与えてくれます。ぜひ、社内研修などでとりあげてみて欲しいと思います。