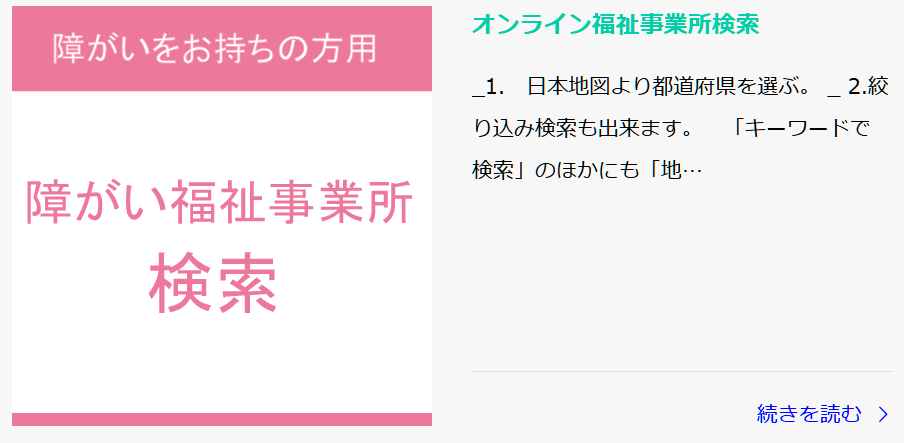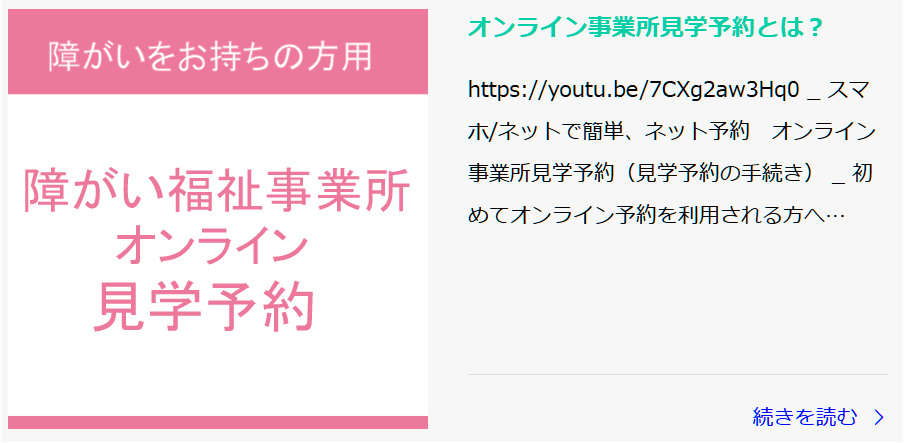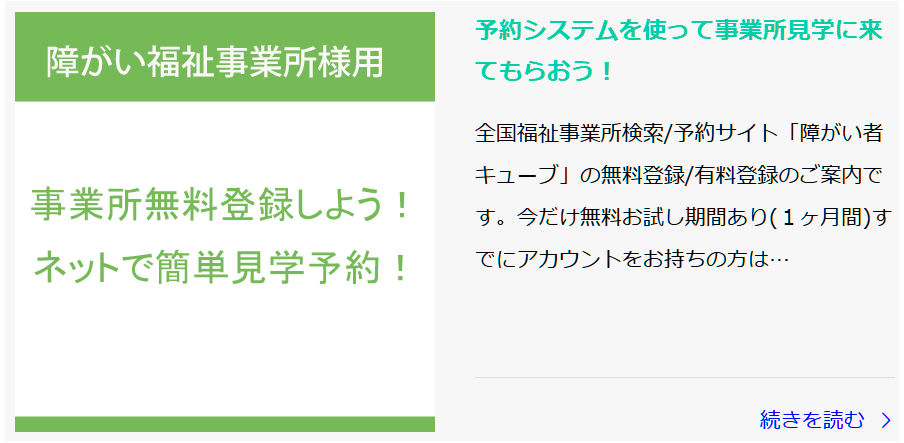・はじめに
適応障害(適応反応症)は、通院されている方が多い疾患の一つです。不適応の要因は、職場の業務過多や人間関係、昇進や異動に伴う環境変化もあれば、結婚や出産、引っ越しなどの生活環境の変化が典型的といえますが、その他にも多くの要因があり、適応障害と診断したとしても、実際にはその要因によって治療経過やアプローチなどは様々です。また当然ながら要因だけでなく、本人の特性も含めて把握することは適応障害に限ったことではありませんが、治療を行っていく上でも非常に重要であるといえます。
尚、ここでは違う話になるので詳しくは論じませんが、最近の動向では適応障害(Adjustment Disorder)は、ICD‐11で、過度のストレス状況によって、過剰な心配や苦痛を生じる思考を反復してしまうとされています。これを「障害」と訳すことは、適応できない人に問題があるという誤解を生むとして、学会は「適応反応症」とする案を示しています。
・ICD-11における適応反応症
世界保健機関(WHO)による約30年ぶりの改訂となるICD-11は、これまでと異なり診断要件が明確化されており、今後が臨床上の有用性が増すのではないかと思われます。
適応反応症は、ストレス因となるライフイベントを経験した後に情緒や行動、認知などの症状に加え、生活や学業、仕事などにおける機能の障害が一定期間持続し、ストレス因がなくなれば症状は軽快していきます。
今までの定義としては、他の精神疾患の診断基準を満たさない場合に診断される除外診断を中心としたものでしたが、ICD-11においては2つの症状が明確に定義づけられました。その2つの症状は、①ストレス因やその結果への囚われ、②適応への失敗です。
以下に今回のICD-11における診断の特徴を記します。
- 特定可能な単一もしくは複数の心理社会的ストレス因に対する不適応反応で、通常はストレス因の1カ月以内に出現する。
- ストレス因への反応の特徴は、ストレス因やその結果についての囚われである。その例には過度の心配、ストレス因への反復的で苦痛な施行、その影響について絶え間ない反芻が挙げられる。
- 症状は、ほかの精神疾患(気分症や他のストレス関連疾患)では十分に説明されない。
- ストレス因とその影響が一旦なくなれば、症状は6カ月以内に消退する。
- ストレス因に対する不適応のために、個人生活、社会生活、学業、仕事、そのほかの重要な機能領域に障害が生じたり、維持するのに多大な努力を要する。
- ストレス因を思い出させるものがあると、囚われの症状は増悪する傾向があり、その結果として囚われや苦痛が起きないようにストレス因に関連する刺激や思考、議論等を回避しようとする。
- 適応反応症に不随する心理社会的な症状として、抑うつまたは不安症状が増悪したり、「外在化」症状として喫煙やアルコール、他の物質の使用の増加が認められる。
- ストレス因がなくなったり、ストレス因への新たな対処法や配慮、対策などを講じることが出来た場合には、通常は適応反応症から回復することができる。
適応反応症におけるストレス因は深刻さや種類の点で様々であり、常に極度の脅威や恐怖を伴うとは限りません。心的外傷後ストレス症の症状要件を満たす場合でもストレス因の深刻さが低い場合は適応反応症と診断されます。また、極度の脅威や恐怖を伴う体験を経験した場合でも、心的外傷後ストレス症の症状要件を満たさず適応反応症と診断されることが多いです。
症状を説明しうる別の精神および行動の障害(一時性精神症、気分障害、ストレス関連障害、パーソナリティー症、強迫症または関連症、全般性不安障害、分離不安障害、自閉症スペクトラム症など)が存在した場合、適応反応症の診断は別途つけるべきではありません。また、ストレス因が消失したあと6か月を超えても症状が持続する場合は、通常は診断の変更が適切と考えられています。
・【診断】
| 1.特定可能な単一もしくは複数の心理社会的ストレス因に対する不適応反応で、通常ストレス因の1カ月以内に発症する。 2.少なくともいずれかのストレス因や結果に対しての囚われといえる。 A)ストレス因に対する過度な心配 B)ストレス因に対しての反復的で苦痛な思考 C)ストレス因の影響についての反芻 3.ストレス因に対する不適応のために、個人生活や社会生活、学業、仕事などの重要な機能領域に有意な障害が生じている。 4.症状が別の精神障害または行動障害の診断を肯定するのに特異性や重症度において不十分である。 5.ストレスの要因が長く持続しない限り、症状は通常6カ月以内に消退する。 |
DSM-5との違いとしてはDSM-5では機能障害を必須としていないのに対し、ICD-11では個人生活や社会生活、学業や仕事などにおける有意な機能障害が必須とされている。また、発症時期との関係性においてもDSM-5ではストレス因から3カ月以内であるのに対しICD-11では1カ月以内と規定されている。
特にDSM-5とICD-11の大きな違いとしては症状の規定です。DSM-5では苦痛を構成する症状をはっきり規定していないのに対し、ICD-11ではストレス因に関する過度な心配や反復的で苦痛な思考、ストレス因の影響についての絶え間ない反芻であると定義されています。
適応反応症(適応障害)は原則的にはあらゆるその他の精神疾患を除外して初めて診断するべき疾患であり、うつ病やPTSDなどとの鑑別診断や正常を診断の際には意識すべき疾患である。
・【治療】
適応反応症の疾患の一般人口を対象とした疫学的研究は非常に少ないため治療に関するエビデンスの蓄積は現状では不十分であり、このため一対一対応的に一般化して強く推奨する治療法を述べることは難しい疾患です。一方で、いくつかの研究では治療において重要な示唆を与えているので、その一例を下記に列挙しておきます。
| ・薬物以外の治療(心理的介入、自己治療、マインドフルネス、認知行動療法etc) ・薬物療法としての各種向精神薬 |
・【復職支援】
適応反応症(適応障害)による休職でも、うつ病と同様にしっかりした休養や必要に応じた薬物療法の導入で、まずは症状緩和に取り組む必要があります。休職しているなかで日常生活が問題なく送れるようになれば、復職の準備を始めることになります。最初に取り組むべきは、生活リズムを立て直すことです。状況によっては日常生活の活動記録表を記録してもらうこともあります。次に行うこととして作業課題の実施です。仕事に準じた作業を実施することで、復職の準備としてもう一段階進むことができます。さらに課題は図書館などで会社の始業時間に合わせて行うなどの方法もあります。
適応反応症の場合は環境への不適応により発症している経緯から、休職中に体調が安定していることは必要条件とは言えますが、生活リズムも整い、作業課題をこなせるようになったとしても、必ずしも復職後の職場への適応を保証するものではなく、不適応に至った要因を特定し、再発予防のための方法などを検討する必要があります。
不適応の要因を特定するためにも経過についての聴き取りをしっかりと行い、病院側で把握する必要があります。そのため初診段階でもある程度時間をかけた診察が必要になります。一方、初診時の症状によっては本人が十分に経過を整理できなかったり、場合によっては話すことも困難な状態まで悪化していたりすることもあったりするので、症状が落ち着いた後にも再度経過を把握する聴き取りを行います。職場での不適応においても、具体的にどのような点が、本人にとって負担となっていたのかを把握するため、職場での昇進などの役割の変化による不適応とケース、上司や部下、同僚との人間関係の問題による不適応のケース、退職者が出たり職場の組織変革に伴い業務時間や業務負荷が増えたことによる不適応など様々なケースがあり、それにより対応をそれぞれ検討する必要があります。
必要であれば、患者の同意が得られれば、職場からの情報を聴取する場合もあります。当然、患者側と職場では立場が異なるため、患者の見立てと職場の見立てが一致しない場合もあります。その場合は、どちらの見解が正しいかをはっきりさせることが目的ではなく(前述のように立場が違うことで見解が異なることは自然なこととしてあり得るため)患者と共有しながら、現実的な対応を検討します。
・最後に……
メンタルヘルスの病気は見えにくい点が問題です。職場でどれだけ対策したとしても、適応反応症を発症する社員が出てしまう可能性は十分に考えられます。環境に適応する能力やストレスの感じ方は人それぞれなのです。しかし、テレワークの普及で働き方が変わる一方、社員が置かれる環境はさらに多様化していのも事実です。この現代社会において、誰が適応障害になってもおかしくはあいません。企業の人事・総務・労務担当者は、社員の適応障害予防に積極的に取り組み、発症者が出た場合は適切なサポートが必要となります。