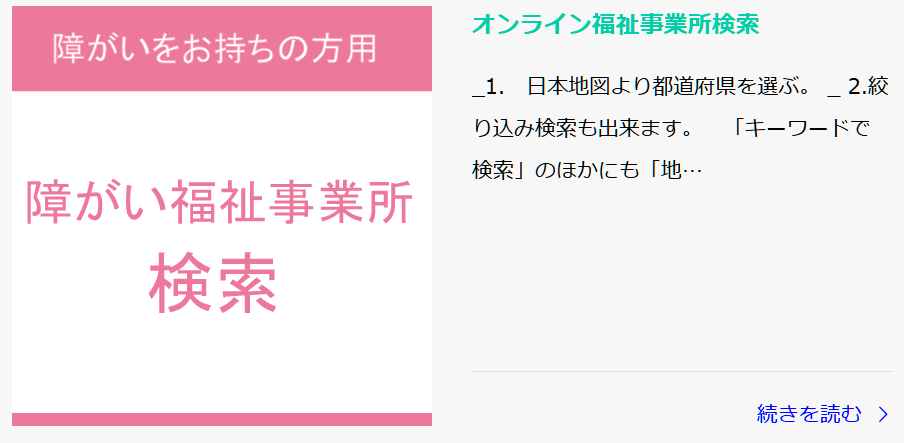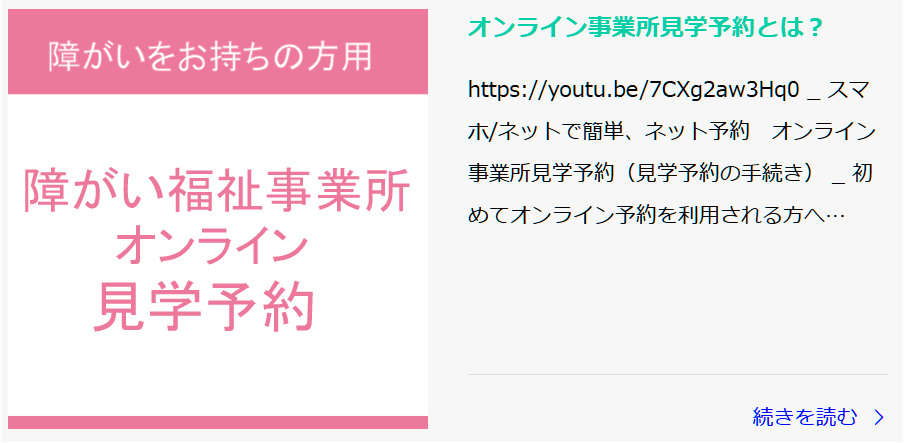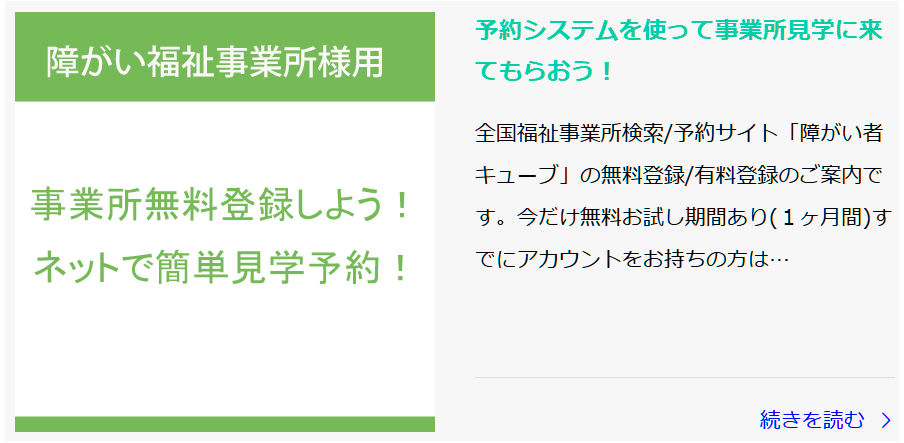・ どんなトラブルが起こり、離職につながるか
企業が障害者を雇用することによって、これまで当たり前だと思っていたことが、当たり前ではないことに気づくという意味では、職場環境が改善されることがあります。しかし、雇用によって起こるトラブルを職場の体質改善につながる財産だと受け止められれば、改善策が実施されることによって障害者のみならず全社員にとっても善き職場環境に生まれ変わっていくはずです。
まずは代表的な事例からトラブルの所在を明確にし、その後で回避するための工夫を紹介します。
精神的な障害者の場合、口頭での指示では、なかなか理解できないという場合があります。
とある企業に就職したAさんは、就職面接の際にそのことを伝えていました。企業側は、最初こそ紙に書いて指示を出していましたが、会議や朝礼などは口頭で行うことが多く、Aさんは今何しているのかわからずもしかしたら「自分にミスがあったのではないか」、「私は必要とされてはいないのではないか」、などという思いがつのりパニックになり、最終的に離職という形になってしまいました。
障害者によっては、指示を1度で理解するのが難しい人や、指示を紙に書いていないとわからない人がいます。特に面接時にそのことが伝えられていたのであれば、企業側は寄り添った対応をすべきでした。
障害者の方に「困っていることや悩んでいることはないですか」と確認したり、部署に紙での指示を出しているのかを確認したり、日々の業務での困りごとのヒアリング不足が招いた事態だといえます。
身体障害者を雇用する際、職場内は車いすや器具で移動しやすい状態になっていることが重要です。例えば、就労スペースが狭くて車いすが通りにくい、階段が多い職場などは注意が必要です。精神障害者の場合、対人恐怖症などで人の目を気にしてしまう人がいるので、就労するスペースや席の配置に注意が必要です。人によっては、両サイドに人がいると追い詰められてしまう人もいるので、席の配置などは注意が必要です。
また、ロッカーの場所が薄暗くてパニックになり、行きたくないと思ってしまうという人も少なくありません。
障害者雇用を行う際に、従業員の障害に対する理解はとても大切です。どうして雇用することにしたのか、どのような仕事をしてもらう予定なのかを事前に従業員に知らせ納得させる必要があります。
「自分よりも簡単な仕事でお金を同じだけもらっている」という想いから、それがいじめに発展したり、仕事がたて込んでいる状態の時、余裕がなくなり上司が「どうしてこんなこともできないんだ」と高圧的なパワハラをしてしまったり、仕事に対する余裕(時間的、精神的)と障害者への理解が足りないと起きてしまうトラブルです。事前に仕事の期限と重要度と伝達しておき、会社全体で障害の対する理解を徹底してもらいたいものです。
・ どうすれば、トラブルが回避でき、定着率を上げることができるのか
(1)こまめな面談
障害者雇用でのトラブルや定着率を上げるために一番有効なのが、面談です。週に1回、月に1回など、定期的に行うことが大切です。現在困っていることや、悩んでいることをヒアリングして、対応が必要な部分には早めに対処することで、トラブルを防止することが出来ます。
・面談の担当はいつも同じ人にする
障害者は、初対面の人に緊張してしまうものです。特に精神障害を持っている人は、周りからの目も気になるので、面談する人が変わると言いたいことが言えなくなってしまう可能性があります。面談をする人事担当を決めて、信頼関係を結ぶことが大切です。
・オープンクエスチョンを避ける
「最近どうですか?」「調子はどうですか?」というような、漠然とした質問は避けるようにしましょう。「今週新たに●●の業務が始まりましたが、困っていることはありませんか?」というように具体的な問いかけをするように心がけてください。
(2)仕事面以外の配慮
障害者が離職するのは、業務や職場の状況が良くないからというだけではありません。
・通勤手段(電車での通勤に耐え切れず離職するというというケースもある)
・人間関係 ・休み時間やお昼の過ごし方
・薬の副作用
(3)従業員からの聞き取り
ヒアリングは障害者本人だけに行うのではなく、一緒に業務をしている人や、上司に確認する必要があります。障害者本人が困っていること、周りの従業員が困っていることがあれば、早めに対処することでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。特に、従業員からの聞き取りで、障害者が言えなかった問題点の抽出が出来ることもあります。
目標をもって、例えば、1年雇用が継続するまでは、丁寧な対応が必要となります。
・ 障害者と働くということ
障害者と共に働くということは、それなりのリスクが伴います。しかしそのリスクは考えようによっては、仕事の見直しや組み立て方、指示の仕方といった、対障害者というだけでなく職場でのリーダー育成的要素がふんだんにあり、全社的に職場環境の改善につながるというのは想像に難くありません。経営者の方針や人事担当者の熱意次第では、プラスに転化できるリスクだといえます。
障害者雇用促進法があるから雇用するという考え方ではなく、せっかく働いてもらうなら本人だけでなく全社員にとって働きやすい環境づくりを行うというような前向きな考え方で取り組むことを薦めます。たとえ障害者雇用に慣れていても、思わぬところでトラブルは起きるものあります。障害は、ひとりひとり症状や困りごとは異なります。それは社員もひとりひとり違った個性があるということにも気づかせてくれます。いうまでもないことですが、職場という公的な場においては、お互いが配慮をしあうことが何より大切です。
・ 障害者雇用の事例
・障害者雇用で企業にとってプラスに働いた事例を紹介します。
| 事業所名 | 事例 | 業種/ 所在地 |
事業内容 | 従業員数 (障害者数) |
| アジア技研株式会社 九州工場 | 多様な人材が会社の戦力であり チームワークを作り出す |
製造業/福岡県北九州市 | スタッド溶接システム製造販売、 工業用ファスナー製造販売、 各種ボイラー向けスタッド溶接責任施工、 マグネシウム合金関連製品 |
38名(4名) |
| 社会福祉法人永平寺町社会福祉協議会 松岡デイサービスセンター |
高齢者施設における視覚障害者の雇用取組事例 ~盲学校と連携し、就労支援機器を活用した取組~ |
医療・福祉業/福井県吉田郡永平寺町 | 通所介護事業の運営 |
27名(2名) |
| 株式会社宮の華 | 企業と従業員の成長につながる障害者雇用 | 製造業/沖繩県宮古島市 |
泡盛、もろみ酢製造・販売 | 11名(1名) 知的障害1名 |
| 岐阜日石株式会社 | ドライバーの安全・快適な生活をサポートし、 地域への貢献、社会との共生を目指す ~ガソリンスタンドにおける障害者雇用から~ |
卸売・小売業/岐阜県岐阜市 | 石油製品販売、自動車整備・鈑金、 自動車販売及び買取・リース、 損害保険代理業、生命保険募集業務 |
166名(5名) 肢体不自由1名 内部障害1名 知的障害1名 精神障害2名 |
| 堀長木材商店 | 柔軟な働き方で、地域社会とつながる雇用に | 製造業/和歌山県西牟婁郡すさみ町 | 製材業 | 6名(2名) 知的障害2名 |
| 九州オルガン針株式会社 | 細やかな情報共有による企業全体としての支援体制の構築 | 製造業/熊本県玉名郡 |
ミシン針製造・精密部品製造販売 |
110名(3名) 肢体不自由1名 知的障害1名 精神障害1名 |
| 秋田ダイハツ販売株式会社 | 企業理念に基づく、障害の有無に関わらず 働きやすい職場環境づくりの取組 |
卸売・小売業/秋田県秋田市 | 自動車販売 | 286名(13名) 聴覚・言語障害2名 肢体不自由1名 内部障害2名 知的障害6名 精神障害2名 |
| 株式会社アオイコーポレーション セントラルキッチン事業部 |
法人内の事業所と就労支援事業所とが 両輪となって生産性向上を目指す |
サービス業/高知県安芸郡芸西村 | 業務委託事業(給食受託、清掃受託)、 介護食品の製造・販売 など |
135名(11名) 肢体不自由1名 知的障害5名 精神障害4名 発達障害1名 |