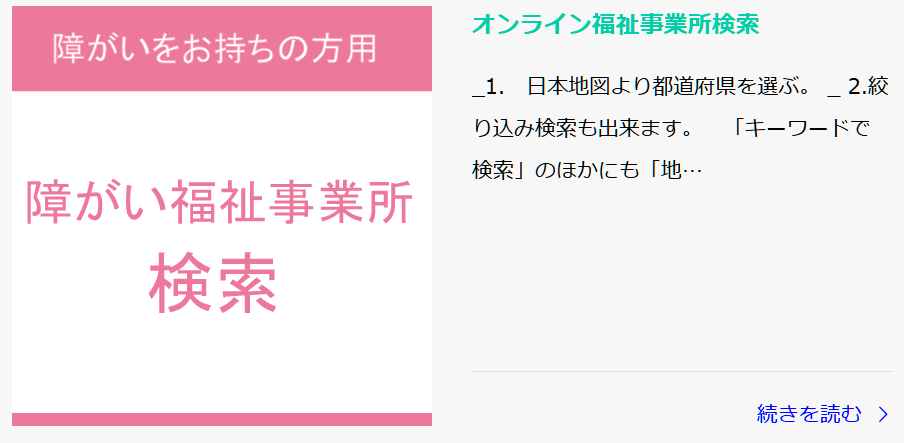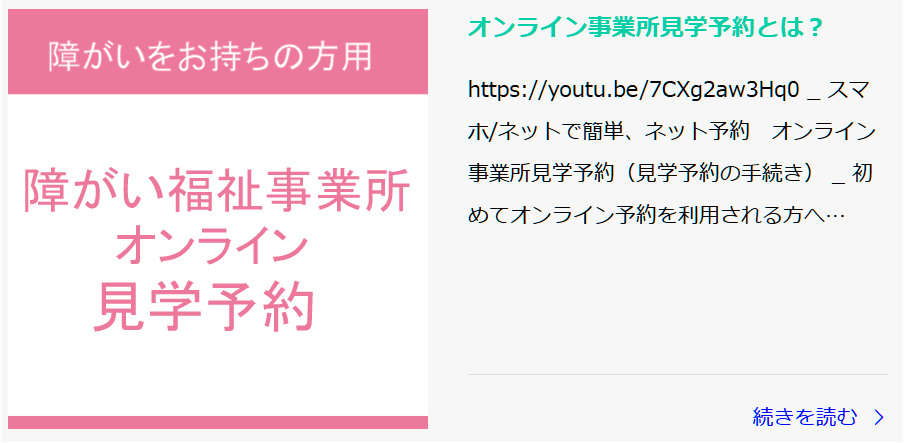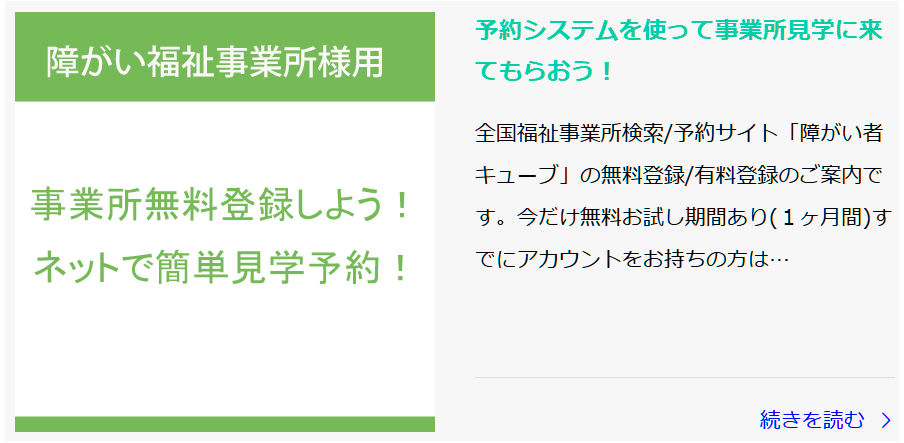消化器について
消化器について
私たちはものを食べ、水分を補給することで、生命を維持するために必要なエネルギーやからだをつくるために必要な原料を得ています。このように食物を体内に取り込み、消化、吸収し、最終的には不要物を排泄するまでの役割をになう器官が消化器です。消化器は、胃や腸はもちろん、食物を取り込む口(口腔)や栄養素を貯蔵・加工する肝臓なども消化器に含まれます。消化器のうち、食物や水分の通り道となる部分が消化管です。
消化管は口腔にはじまり、咽頭、食道、胃、小腸(十二指腸、空腸、回腸)大腸、肛門までを指し、全長は約6mです。食物はこの消化管を通り、消化・吸収され、やがて流動体の残りかす(不要物)が大腸で糞便となり、排泄されます。
《消化管の働き》
口:食物が口内で咀嚼される間に、唾液と混ざり、唾液アミラーゼにより、デンプンの消化が始まります。
食道、胃、十二指腸:食物は食道を通過し胃に到達すると、一旦胃内に貯留し撹拌(かくはん)され、胃液中の酵素や酸によってタンパク質の消化が始まります。
小腸:胃で撹拌された食物は十二指腸に流れ込み、そこで膵液や胆汁と混ざり、さらに各種酵素の消化作用を受けつつ、小腸内を移動していきます。この移動の間に各種栄養素が吸収されます。
大腸:大腸では水と電解質が吸収され、消化吸収されなかったものや老廃物を肛門まで運搬します。
消化管は口腔にはじまり、咽頭、食道、胃、小腸(十二指腸、空腸、回腸)大腸、肛門までを指し、全長は約6mです。食物はこの消化管を通り、消化・吸収され、やがて流動体の残りかす(不要物)が大腸で糞便となり、排泄されます。
《消化管の働き》
口:食物が口内で咀嚼される間に、唾液と混ざり、唾液アミラーゼにより、デンプンの消化が始まります。
食道、胃、十二指腸:食物は食道を通過し胃に到達すると、一旦胃内に貯留し撹拌(かくはん)され、胃液中の酵素や酸によってタンパク質の消化が始まります。
小腸:胃で撹拌された食物は十二指腸に流れ込み、そこで膵液や胆汁と混ざり、さらに各種酵素の消化作用を受けつつ、小腸内を移動していきます。この移動の間に各種栄養素が吸収されます。
大腸:大腸では水と電解質が吸収され、消化吸収されなかったものや老廃物を肛門まで運搬します。
 消化器疾患
消化器疾患
消化器疾患は、上記で説明した消火器の一部が何らかの原因によって異常をきたす疾患の総称です。生活様式の変化やストレスの増加などによって、消化器の癌を含めた消化器疾患の患者は年々増加してきており、それに伴い、日本において特定医療費の助成対象となる指定難病である潰瘍性大腸炎(主に大腸粘膜に潰瘍やびらんができる原因不明の非特異性炎症性疾患)やクローン病(口腔から肛門までの全消化管に、非連続性の慢性肉芽腫性炎症を生じる原因不明の炎症性疾患)、原発性胆汁性胆管炎(胆汁鬱滞型の肝硬変を呈する疾患)、自己免疫性肝炎(免疫システムの異常により、肝臓に障害が起こる自己免疫疾患の一つ)などの患者も、近年増加しています。
主な疾患と特徴
 1.炎症性腸疾患
1.炎症性腸疾患
大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍をひきおこす原因不明の疾患の総称を炎症性腸疾患といい、潰瘍性大腸炎とクローン病が含まれます。日本における患者数は、2020年度末現在で両疾患を合わせておよそ20万人であり、近年増加傾向にあります。
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜(最も内側の層)にびらんや潰瘍(粘膜が欠損すること)ができる大腸の炎症性疾患です。特徴的な症状としては、血便を伴うまたは伴わない下痢とよく起こる腹痛です。病変は直腸から連続的に、そして上行性(口側)に広がる性質があり、最大で直腸から結腸全体に拡がります。この病気は病変の拡がりや経過などにより下記のように分類されます。
病変の拡がりによる分類:全大腸炎型、左側大腸炎型、直腸炎型
病期の分類:活動期、寛解期
重症度による分類:軽症、中等症、重症、激症
臨床経過による分類:再燃寛解型、慢性持続型、急性激症型、初回発作型
この病気では継続的に症状が出ることは少なく、寛解期(症状が落ち着いている時期)と再燃期(一時的または長い期間引き続いて軽快または消失していた疾病が、再び悪化または出現してくること)を繰り返すことが特徴で、またそのペースも個人によって異なります。 症状としては、下痢(便が軟らかくなって、回数が増えること)や血便が認められます。痙攣性または持続的な腹痛を伴うこともあります。重症になると、発熱、体重減少、貧血などの全身の症状が起こります。また、腸管以外の合併症として、皮膚の症状、関節や眼の症状が出現することもあります。 この疾患の患者さんには、原則的には薬による内科的治療が行われます。治療の目的は大腸粘膜の異常な炎症を抑え、症状をコントロールすることです。潰瘍性大腸炎の内科的治療には主に以下のものがあります。
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜(最も内側の層)にびらんや潰瘍(粘膜が欠損すること)ができる大腸の炎症性疾患です。特徴的な症状としては、血便を伴うまたは伴わない下痢とよく起こる腹痛です。病変は直腸から連続的に、そして上行性(口側)に広がる性質があり、最大で直腸から結腸全体に拡がります。この病気は病変の拡がりや経過などにより下記のように分類されます。
病変の拡がりによる分類:全大腸炎型、左側大腸炎型、直腸炎型
病期の分類:活動期、寛解期
重症度による分類:軽症、中等症、重症、激症
臨床経過による分類:再燃寛解型、慢性持続型、急性激症型、初回発作型
この病気では継続的に症状が出ることは少なく、寛解期(症状が落ち着いている時期)と再燃期(一時的または長い期間引き続いて軽快または消失していた疾病が、再び悪化または出現してくること)を繰り返すことが特徴で、またそのペースも個人によって異なります。 症状としては、下痢(便が軟らかくなって、回数が増えること)や血便が認められます。痙攣性または持続的な腹痛を伴うこともあります。重症になると、発熱、体重減少、貧血などの全身の症状が起こります。また、腸管以外の合併症として、皮膚の症状、関節や眼の症状が出現することもあります。 この疾患の患者さんには、原則的には薬による内科的治療が行われます。治療の目的は大腸粘膜の異常な炎症を抑え、症状をコントロールすることです。潰瘍性大腸炎の内科的治療には主に以下のものがあります。
5-ASA製薬には従来からのサラゾスルファピリジン(サラゾピリン)と、その副作用を軽減するために開発された改良新薬のメサラジン(ペンタサ、アサコール、リアルダ)があります。経口や直腸から投与され、持続する炎症を抑えます。炎症を抑えることで、下痢、血便、腹痛などの症状は著しく減少します。5-ASA製薬は軽症から中等症の潰瘍性大腸炎に有効で、再燃予防にも効果があります。
代表的な薬剤としてプレドニゾロン(プレドニン)があります。経口や直腸からあるいは経静脈的に投与されます。この薬剤は中等症から重症の患者さんに用いられ、強力に炎症を抑えますが、再燃を予防する効果は認められていません。最近では、肝臓で速やかに分解されるブデソニドという新しいステロイドを使った注腸製剤も使われています。
薬物療法ではありませんが、血液中から異常に活性化した白血球を取り除く治療法で、GCAP(顆粒球除去療法:アダカラム)、血球細胞除去用浄化器(イムノピュア)があります。副腎皮質ステロイド薬で効果が得られない患者さんの活動期の治療に用いられます。
アザチオプリン(イムラン、アザニン)や6-メルカプトプリン(ロイケリン)(未承認)はステロイド薬を中止すると悪化してしまう患者さんに有効です。また、シクロスポリン(サンディミュン)(未承認)やタクロリムス(プログラフ)はステロイド薬が無効の患者さんに用いられます。
インフリキシマブ(レミケード)、アダリムマブ(ヒュミラ)、ゴリムマブ(シンポニー)といった注射薬が使用されます。効果が認められた場合は、インフリキシマブは8週ごとの点滴投与、アダリムマブでは、2週ごとの皮下投与、ゴリムマブでは4週ごとの投与が行われます。アダリムマブとゴリムマブでは自己注射も可能です。
ウステキヌマブ(ステラーラ)は炎症を引き起こす分子であるインターロイキン12およびインターロイキン23を抑えます。ウステキヌマブは12週ごとの皮下投与が行われます。
ヤヌスキナーゼ阻害薬であるトファシチニブ(ゼルヤンツ)は免疫細胞に作用して炎症を抑えます。トファシチニブは経口投与で用いられます。
多くの場合、内科治療で症状が改善しますが、内科治療が無効な場合(特に重症例)や副作用などで内科治療が行えない場合、大量の出血、穿孔(大腸に穴があくこと)、癌またはその疑いがあるなどの場合には外科手術(大腸全摘術)が行われます。大腸全摘術の際には、小腸で人工肛門を作る場合もありますが、近年では、小腸で便をためる袋(回腸嚢)を作成して肛門につなぐ手術が主流となっています。その場合、術後は普通の人とほぼ同様の生活を送ることができます。
多くの患者さんでは、治療を続けることで症状の改善や消失(寛解)が認められますが、再発する場合も多く、寛解を維持するために継続的な内科治療が必要です。また、あらゆる内科治療で寛解とならずに手術が必要となる患者さんもいます。また、発病して7-8年すると大腸癌を合併するリスクが高くなってきますので、そのような患者さんでは、症状がなくても定期的な内視鏡検査が必要になります。しかし、実際に、一生のうちに大腸癌を合併する患者さんはごく一部です。重症で外科手術になる患者さんなど一部の患者さんを除けば、ほとんどの患者さんの生命予後は健常人と同等です。
対して、クローン病は口腔にはじまり肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍が起こりえますが、小腸と大腸を中心として特に小腸末端部が好発部位であるといえます。非連続性の病変(病変と病変の間に正常部分が存在すること)を特徴とします。
症状は患者さんによってさまざまで、侵される病変部位(小腸型、小腸・大腸型、大腸型)によっても異なります。その中でも特徴的な症状は腹痛と下痢で、半数以上の患者さんでみられます。さらに発熱、下血、腹部腫瘤、体重減少、全身倦怠感、貧血などの症状もしばしば現れます。また瘻孔、狭窄、膿瘍などの腸管の合併症や関節炎、虹彩炎、結節性紅斑、肛門部病変などの腸管外の合併症も多く、これらの有無により様々な症状を呈します。
治療は、栄養療法や薬物療法などの内科治療と外科治療があります。内科治療が主体となることが多いのですが、腸閉塞や穿孔、膿瘍などの合併症には外科治療が必要となります。栄養療法と食事療法では、栄養状態の改善だけでなく、腸管の安静と食事からの刺激を取り除くことで腹痛や下痢などの症状の改善と消化管病変の改善が認められます。
栄養療法には経腸栄養と完全中心静脈栄養があります。経腸栄養療法は、抗原性を示さないアミノ酸を主体として脂肪をほとんど含まない成分栄養剤と少量のタンパク質と脂肪含量がやや多い消化態栄養剤があります。完全中心静脈栄養は高度な狭窄がある場合、広範囲な小腸病変が存在する場合、経腸栄養療法を行えない場合などに用いられます。病気の活動性や症状が落ち着いていれば、通常の食事が可能ですが、食事による病態の悪化を避けることが最も重要なことです。調子の悪いときには低脂肪・低残渣の食事が奨められていますが、個々の患者さんで病変部位や消化吸収機能が異なっているため、主治医や栄養士と相談しながら自分にあった食品を見つけていくことが非常に大切です。
症状のある活動期には内科的治療として、主に5-アミノサリチル酸製薬(ペンタサやサラゾピリン)、副腎皮質ステロイドや免疫調節薬(イムランなど)などの内服薬が用いられます。5-アミノサリチル酸製薬と免疫調節薬は、症状が改善しても、再燃予防のために継続して投与が行われます。また、これらの治療が無効であった場合には、抗TNFα受容体拮抗薬(レミケードやヒュミラ)、抗インターロイキン12/23p40抗体(ステラーラ)、抗α4β7インテグリン抗体(エンタイビオ)などが使用されます。薬物治療ではありませんが、血球成分除去療法が行われることもあります。
高度の狭窄や穿孔、膿瘍などの合併症に対しては外科治療が行われます。その際には腸管をできるだけ温存するために、小範囲の切除や狭窄形成術などが行われます。クローン病の合併症のうち、狭窄に対しては、内視鏡的に狭窄部を拡張する治療が行われることもあります。
ごく最近まで、クローン病のほとんどの患者さんが、一生のうちに一度は、外科手術が必要になると言われてきました。しかし近年の治療の進歩により、手術をする患者さんが減ってきていることが明らかになってきています。多くの患者さんで、寛解導入は可能となってきていますが、いっけん症状が落ち着いていても、ひそかに病気は進行すると言われています。治療を継続しつつ、定期的な画像検査などの病気の状態を把握することはきわめて大切です。
日常生活では、おなかの調子がよい時期でも食事には注意が必要です。動物性脂肪の取りすぎはおなかの炎症を悪化させる可能性があることを忘れないことが大切です。また、おなかの調子が良くても病気が悪化していることもありますから、やはり定期的に内視鏡などの検査を受けることが大切です。
 2.原発性胆汁性胆管炎(PBC)
2.原発性胆汁性胆管炎(PBC)
肝臓は「人体の工場」といわれるほどいろいろな働きをしていますが、その中の一つに胆汁という消化液をつくるという働きがあります。胆汁は肝臓の中の肝細胞という細胞によってつくられたあと、胆管を通り、いったん胆嚢で蓄えられた後十二指腸に流れこみます。
原発性胆汁性胆管炎(げんぱつせいたんじゅうせいたんかんえん)という病気は、肝臓の中のとても細い胆管が壊れる病気です。英語ではPrimary Biliary Cholangitisといい、頭文字をとってPBCと呼ばれています。肝臓の中のとても細い胆管が壊れるため、胆汁の流れが通常よりも少し滞ってしまい、血液検査をするとALPやγGTPなどの胆道系酵素が通常よりもかなり高い数値になります。血液の中に抗ミトコンドリア抗体(AMA)という自己抗体が検出されるのがPBCの特徴であり、このことなどからこの病気の原因として、免疫反応の異常、すなわち、自己免疫反応が関与する自己免疫疾患であることが、国内外の研究で明らかになりつつあります。患者の男女比は約1:4で、20歳以降から徐々に数が多くなり、50~60歳に最も多くみられます。
現在PBCと診断される方の多くはまだ病気が進行しておらず、肝硬変へ至っていません。この段階であれば肝臓の中の胆汁の流れは多少滞ってはいるもののまだまだ十分に保たれていますし、肝臓の働きも正常ですので、自覚症状はほとんどありません。ただ、このような軽い段階の方でも、およそ30%程度の患者さんは中等度から重度の皮膚のかゆみを自覚しておられることが分かっています。
原発性胆汁性胆管炎(げんぱつせいたんじゅうせいたんかんえん)という病気は、肝臓の中のとても細い胆管が壊れる病気です。英語ではPrimary Biliary Cholangitisといい、頭文字をとってPBCと呼ばれています。肝臓の中のとても細い胆管が壊れるため、胆汁の流れが通常よりも少し滞ってしまい、血液検査をするとALPやγGTPなどの胆道系酵素が通常よりもかなり高い数値になります。血液の中に抗ミトコンドリア抗体(AMA)という自己抗体が検出されるのがPBCの特徴であり、このことなどからこの病気の原因として、免疫反応の異常、すなわち、自己免疫反応が関与する自己免疫疾患であることが、国内外の研究で明らかになりつつあります。患者の男女比は約1:4で、20歳以降から徐々に数が多くなり、50~60歳に最も多くみられます。
現在PBCと診断される方の多くはまだ病気が進行しておらず、肝硬変へ至っていません。この段階であれば肝臓の中の胆汁の流れは多少滞ってはいるもののまだまだ十分に保たれていますし、肝臓の働きも正常ですので、自覚症状はほとんどありません。ただ、このような軽い段階の方でも、およそ30%程度の患者さんは中等度から重度の皮膚のかゆみを自覚しておられることが分かっています。
この段階でPBCと診断されず、治療が行われない場合、さらに進行していきます。すなわち、肝臓の中の小さな胆管がさらに破壊され、胆汁の流れが一層悪くなります。すると、胆汁に含まれる成分が血液中に逆流するため全身の強いかゆみが起こります。また、食道・胃静脈瘤という合併症も起こります。強い疲れやすさやだるさを感じることもあります。肝臓の中では胆管だけではなく肝細胞も破壊され、徐々に肝硬変へと進行します。
また、食物中のビタミンDを吸収するために必要な胆汁が流れにくくなるため、ビタミンDが吸収されにくくなり、特に閉経期の女性では骨粗鬆症が進行しやすくなります。また、やはり胆汁が流れにくくなる結果血中コレステロールが上昇し、目の周りに脂肪が沈着する眼瞼黄色種ができることもあります。さらに肝臓の働きが低下すると、黄疸、浮腫(むくみ)や腹水、肝性脳症を発症して肝不全となり、肝移植を行わない限り救命できない状態に陥ってしまうこともあります。一部の患者さんでは肝臓に癌ができることもあります。
また、食物中のビタミンDを吸収するために必要な胆汁が流れにくくなるため、ビタミンDが吸収されにくくなり、特に閉経期の女性では骨粗鬆症が進行しやすくなります。また、やはり胆汁が流れにくくなる結果血中コレステロールが上昇し、目の周りに脂肪が沈着する眼瞼黄色種ができることもあります。さらに肝臓の働きが低下すると、黄疸、浮腫(むくみ)や腹水、肝性脳症を発症して肝不全となり、肝移植を行わない限り救命できない状態に陥ってしまうこともあります。一部の患者さんでは肝臓に癌ができることもあります。
一方、自己免疫を起こしやすい体質の方では胆管だけではなく他の組織・細胞も自己免疫によって攻撃されることがあるため、PBCには他の自己免疫疾患がしばしば合併することが知られています。日本ではPBCの約15%の方に涙や唾液が出にくくなり、口や眼が乾燥するシェーグレン症候群、約5%に関節リウマチ、慢性甲状腺炎が合併するとされており、これら他の自己免疫疾患の症状が目立つ場合もあります。
PBCの治療は、胆汁の流れを良くして肝硬変への進行を抑えるというPBCそのものに対する治療と、PBCに伴って生じる症状や合併症に対しての治療に大別できます。
PBCそのものに対する治療としては、ウルソデオキシコ-ル酸という薬に胆汁の流れを促進し病気の進行を抑える働きがあることが分かり、現在PBCに対して世界中で使われています。ウルソデオキシコール酸が使用されるようになってから、PBCの経過は明らかに改善しました。ほとんど症状のない無症候性PBCの患者さんでは、これらの薬を飲み続けることによって、病気のない方と同じく日常生活を送り天寿を全うすることができるようになっています。ウルソデオキシコール酸だけで十分に肝機能障害が改善しない場合、わが国ではベザフィブラートという薬がしばしば使われます。ベザフィブラートはPBCに対する使用は正式には認められてはいませんが、研究班によってベザフィブラートとウルソデオキシコール酸との併用によって、PBCの長期予後が改善されている可能性を確認しています。
PBCに伴って生じる症状や合併症に対しての治療としては、まず強いかゆみに対して抗ヒスタミン薬が使われます。最近は肝臓病で起こるかゆみに対する新しい薬(ナルフラフィン塩酸塩)が開発されており、PBCのかゆみについても一定の効果が認められています。ビタミンDの吸収障害による骨粗鬆症に対しては、ビスホスホネート製剤やデノスマブなど多くの薬が開発されています。
PBCが進行して肝硬変に至った場合は、他の原因による肝硬変と同じ治療を行います。しかし、これら様々な内科的治療を行ってもなおその効果がみられない場合、肝移植治療を検討します。身内に肝臓を提供する方がいらっしゃる場合は生体部分肝移植が行われます。また、脳死肝移植を受けられる方も少しずつ多くなってきていますが、この場合脳死肝移植の登録が必要となります。PBCの場合、肝移植を行った後の経過は良好です。
ほとんど症状がなく、血液検査だけに異常がみられるという無症候性PBCの方は、薬を飲み続けていただければ日常生活の中で特別の注意は必要ありません。安静にする必要はありませんし、仕事も他の人と同じようにすることができます。最近では、肥満にならないように食事のエネルギー制限や適度な運動が必要な方が増えています。ただ、薬の服用を止めてしまうと病気の進行が進む可能性がありますので、病院への定期的な通院と薬の服用は続けてください。
病気が進行して肝硬変の状態に至ってしまった場合には、食事や運動など日常生活の中でもう少しきめ細かい注意が必要になりますので、主治医とよく相談することが大切です。また肝移植治療にあたっては、主治医によく相談した上で専門の施設に紹介してもらうことが必要になってきます。
 3.自己免疫性肝炎
3.自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎は、多くの場合には慢性に経過する肝炎で、肝細胞が障害される疾患です。血液検査では肝臓の細胞が破壊される程度を表すASTやALTが上昇します。自己免疫性肝炎が発病するのには免疫の異常が関係していると考えられています。
治療では副腎皮質ステロイドが有効です。英語での病名はAutoimmunehepatitisであり、頭文字を略してAIHと呼ばれます。患者の男女比は1:4で、女性に多い病気です。中年女性に多く50歳から60歳代が発症の中心となっていますが、若い女性や小児での発症も珍しくはありません。近年の傾向として男性の患者さんが以前よりも増えており、また高齢化が示されています。
治療では副腎皮質ステロイドが有効です。英語での病名はAutoimmunehepatitisであり、頭文字を略してAIHと呼ばれます。患者の男女比は1:4で、女性に多い病気です。中年女性に多く50歳から60歳代が発症の中心となっていますが、若い女性や小児での発症も珍しくはありません。近年の傾向として男性の患者さんが以前よりも増えており、また高齢化が示されています。
原因は不明ですが、血液検査で自己抗体(抗核抗体や抗平滑筋抗体)が陽性で免疫グロブリン、ことにIgGの血中濃度が高く、副腎皮質ステロイドによる治療によく反応することなどから、自己免疫が関与していると考えられています。肝臓の組織検査でもリンパ球が多数肝内に存在し、肝細胞が障害されている像が認められます。ウイルス感染や薬剤服用、妊娠・出産後に発症する場合もあり、これらが発症の引き金となる可能性が報告されています。
日本人では60%の症例でHLA-DR4陽性、欧米ではHLA-DR3とHLA-DR4陽性例が多いことから、その発症に何らかの遺伝的因子が関与していると思われます。しかし、国内外の研究により発症に関与している遺伝子がいくつか見出されているPBCとは異なり、AIHの発症に関与することが明確な遺伝子は見つかっていません。親子や兄弟など家族内で発症する例もありますがごくまれです。
発症はとてもゆっくりであり、自覚症状も軽い場合が多いため、通常自ら発症に気がつくことはなく、健康診断などで偶然に発見されることがしばしばあります。しかし、治療を行わないとその進行は早く、肝硬変から肝不全に至ることも稀ではありません。適切な治療を施された患者さんのほとんどでは、肝臓の炎症が速やかに改善し、進行もみられなくなります。
日本での調査では、適切な治療を受け、肝機能検査値が安定している自己免疫性肝炎患者さんの長期予後は良好で、死亡率は一般人口の死亡率と差のないことが示されています。ただ、頻回に肝機能検査値が悪化する患者さんの中には予後不良な方も存在し、肝不全や肝細胞癌を発症する場合があります。
日本での調査では、適切な治療を受け、肝機能検査値が安定している自己免疫性肝炎患者さんの長期予後は良好で、死亡率は一般人口の死亡率と差のないことが示されています。ただ、頻回に肝機能検査値が悪化する患者さんの中には予後不良な方も存在し、肝不全や肝細胞癌を発症する場合があります。
通常は自覚症状がなく、健診などで偶然発見されることが多いようです。全身倦怠感、疲労感、食欲不振などの症状を訴える方もおられます。急性肝炎として発症する場合は、倦怠感、黄疸、食欲不振などの症状がみられますが、自己免疫性肝炎に特徴的な症状はありません。病気が進行した状態で発見される場合もあり、肝硬変へ進行した状態では、下肢のむくみ、腹水による腹部の張りや吐血(食道静脈瘤からの出血)などの症状がおきることがあります。
治療の基本は免疫抑制薬の内服で、まず副腎皮質ステロイドという飲み薬を使用します。副腎皮質ステロイドであるプレドニゾロンを、発症時には30~40mg/日(病状が重い場合には50~60mg/日)服用します。これによって肝機能検査値は改善しますので、推移を見ながらプレドニゾロンの量を5~10mg/日までゆっくり減らします。治療の目標は肝機能検査値、ことにALTとIgGの正常化です。当初から、あるいはプレドニゾロンの減量中に、アザチオプリンという別の薬を50~100mg/日で一緒に服用する場合もあり、これによってプレドニゾロンの減量を早めたり、中止したりできる場合があります。
ただ、副腎皮質ステロイドあるいはアザチオプリンを両方とも完全に中止すると、多くの場合疾患が再燃し、肝機能検査値が再び悪化してしまうため、数値が安定する最低量のプレドニゾロンないしアザチオプリンを維持量として、長期間内服する必要があります。減量の途中、あるいは維持量内服中に病気が再燃した場合は、副腎皮質ステロイドの増量やアザチオプリンの併用を考慮します。
ただ、副腎皮質ステロイドあるいはアザチオプリンを両方とも完全に中止すると、多くの場合疾患が再燃し、肝機能検査値が再び悪化してしまうため、数値が安定する最低量のプレドニゾロンないしアザチオプリンを維持量として、長期間内服する必要があります。減量の途中、あるいは維持量内服中に病気が再燃した場合は、副腎皮質ステロイドの増量やアザチオプリンの併用を考慮します。
副腎皮質ステロイド内服中は、消化性潰瘍、満月様顔貌、糖尿病、脂質異常症、骨粗鬆症などの副作用が出現することがあります。アザチオプリンは比較的副作用の少ない薬ですが、それでも血液の中の白血球・血小板の数が急激に減ってしまうことがあります。これら副作用についてもよく理解し、病態に応じて予防薬投与を受けることも大切です。ことに中年以降の女性の方は骨粗鬆症を発症するリスクが高いので、定期的に骨密度検査を受け、低下している場合には骨密度を改善する薬が必要になります。副腎皮質ステロイド・アザチオプリンなど免疫抑制薬の自己判断による中止は疾患の再燃につながるため、きちんと服用することが大切です。
副腎皮質ステロイドには、副作用として食欲亢進や肥満、糖尿病、脂質異常症が出現することがあります。したがって、食事の量に気をつけ、高カロリー食を避け、体重が増えないようにすることが大切です。比較的多量(15~20mg/日以上)のプレドニゾロンを内服している場合には、何らかの病原体に感染するリスクを避けるため、人の多いところへ出かける時にはマスクを着用したり、粉塵の多い場所を避けたりすることが必要なこともあります。一方、維持量(5~10mg/日)のプレドニゾロンの内服であれば感染を含め日常生活で特別な注意は不要ですし、仕事・旅行なども制限はありません。
予防接種については、不活化ワクチン(インフルエンザ、肺炎球菌、B型肝炎など)やトキソイドワクチン(ジフテリア、破傷風など)、mRNAワクチン(新型コロナウイルス感染症)は接種可能です。副腎皮質ステロイドなど免疫抑制薬での治療中には予防効果が少ないことがありますが、その反面ワクチンを接種せずインフルエンザなどに感染してしまった場合、免疫抑制薬の影響で重症化してしまう危険もありますので、ワクチンを接種されることをお勧めします。一方、生ワクチン(麻疹、風疹、おたふくなど)は、副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬を服用している場合は、原則として接種できません。
自己免疫性肝炎は、妊娠中は病気の落ち着くことが多いですが、出産後に病気が悪化し肝機能検査値が上昇する場合がありますので、主治医の先生および産科の先生とよく相談してください。5~10mg/日程度の副腎皮質ステロイドの服用は妊娠・出産には影響はないと考えられています。アザチオプリンについては、以前は妊娠中には服用してはいけない薬と位置づけられていましたが、比較的安全であることが確認され、2018年7月から治療上必要な場合には妊婦の方が服用することもできるようになりました。
 ・Q&A
・Q&A
A1.動揺(「まさか自分がこんな病気になるなんて想像もできなかった」)→絶望感(「こんな病気になるくらいなら死んだほうがましだ」、「これから一生こんなつらい苦しみと戦い続けなければならないのか」)→不安感(「これからどうやって生きていったらいいんだろう」)。多くの人は医者から障害や難病を告げられた時、少なからずこのようなネガティブな感情に支配されてしまうのではないでしょうか。ましてやそれが、自分がよく知りもしない難病などとなると不安も倍増してしまいます。
難病は、その字のイメージや先入観から「一生治らない」とか「ずっと寝たきり」とか「死んでしまう」といったマイナスのイメージが根強く存在しているのも確かです。事実として、数十年前まではそのような病気もありました。ですが今は違います。医学の進歩によって、難病は「治らない病気」ではなくなったのです。今や難病によって命を落とす人はごくわずかで、多くの人は適切な治療を続けることで他の人と何ら変わらない生活を送ることもできるようになりました。適切な治療を受け、適切な薬を適切な量で使用することで、症状は落ち着き、病気を発症する前とほとんど同じ生活を送ることができます。
そうしているうちに、あることに気づくことができるはずです。それは「難病」や「障害」という言葉のマイナスなイメージに惑わされる必要はないということです。周囲の人の温かさや医学による支援を受けて、今、自分が元気に生活しているのであれば、それは言ってしまえばもはや病気を克服したことと同じことではないかと思うのです。このように、病気と向き合い、気持ちの変化を受け入れ、上手に生活している人がたくさんいます。
一方、行動面では、なるべくストレスをかけないように生活するようになったという人が多いようです。難病とストレスの因果関係が医学的にはっきりと証明されたわけではありませんし、ストレスがたまると絶対に病気にかかるということはありません。しかし、定期的な運動やヨガなどのリラクゼーション、ややぬるめの湯にじっくりつかる入浴などストレスを癒すことは、自分の体をいたわることにもつながり、それまでの自分がいかに自分自身の体を大切にしていなかったかということに気づくこともできるでしょう。また精神と身体はつながっていて、心に負担をかけることは身体にも影響を及ぼします。他人からどう思われるかを必要以上に気にしたり、必要以上に罪悪感を持って自分を責めたりなど、深く悩みすぎることは心と体に負担をかけることになります。性格によっては難しいことかもしれませんが、適度に息抜きなどをして深く考えすぎないこと、もっと自分にやさしくなることも、重要なことかもしれません。
難病は、その字のイメージや先入観から「一生治らない」とか「ずっと寝たきり」とか「死んでしまう」といったマイナスのイメージが根強く存在しているのも確かです。事実として、数十年前まではそのような病気もありました。ですが今は違います。医学の進歩によって、難病は「治らない病気」ではなくなったのです。今や難病によって命を落とす人はごくわずかで、多くの人は適切な治療を続けることで他の人と何ら変わらない生活を送ることもできるようになりました。適切な治療を受け、適切な薬を適切な量で使用することで、症状は落ち着き、病気を発症する前とほとんど同じ生活を送ることができます。
そうしているうちに、あることに気づくことができるはずです。それは「難病」や「障害」という言葉のマイナスなイメージに惑わされる必要はないということです。周囲の人の温かさや医学による支援を受けて、今、自分が元気に生活しているのであれば、それは言ってしまえばもはや病気を克服したことと同じことではないかと思うのです。このように、病気と向き合い、気持ちの変化を受け入れ、上手に生活している人がたくさんいます。
一方、行動面では、なるべくストレスをかけないように生活するようになったという人が多いようです。難病とストレスの因果関係が医学的にはっきりと証明されたわけではありませんし、ストレスがたまると絶対に病気にかかるということはありません。しかし、定期的な運動やヨガなどのリラクゼーション、ややぬるめの湯にじっくりつかる入浴などストレスを癒すことは、自分の体をいたわることにもつながり、それまでの自分がいかに自分自身の体を大切にしていなかったかということに気づくこともできるでしょう。また精神と身体はつながっていて、心に負担をかけることは身体にも影響を及ぼします。他人からどう思われるかを必要以上に気にしたり、必要以上に罪悪感を持って自分を責めたりなど、深く悩みすぎることは心と体に負担をかけることになります。性格によっては難しいことかもしれませんが、適度に息抜きなどをして深く考えすぎないこと、もっと自分にやさしくなることも、重要なことかもしれません。
A2.これまでもお話ししてきたとおり、病気は本人がいかに積極的に治療に取り組むかで、その症状や進行度合いが大きく異なってきます。いかに医学が進歩したとはいえ、本人が自ら治療に取り組まなければ、病気はどんどん悪くなってしまいます。 そこで、少しでも前向きに、楽しく治療や服薬に取り組むためにそれぞれに工夫を行っています。たとえば服薬は、ともすると億劫でまた忘れがちです。そんなつらい服薬を少しでも楽しいものにするために、薬を入れるピルケースを自分好みに、オシャレやかわいさを追求したものにして、楽しい気持ちで服薬している人もいます。また、IBD(炎症性腸疾患))ステーションなどのHPのたべものガイドを見て、おなかに優しいレシピを参考に楽しく料理を作ったりもしています。個人差はありますが、料理は気分転換やストレス解消にいいという人もいます。
また最近では、同じ病気を持つ人が気軽に集まって話し合える場が徐々に増えてきています。難病や障害の中には見た目ではわからないものも多くあり、他人からなかなか理解されにくいのが現状です。ですが、同じ病気を抱えている人どうしで悩みを分かち合い、また励ましあい支えあうことで、前向きに治療に取り組む原動力にもなります。
〇IBDネットワーク加盟会に公開している患者会
【北海道・東北エリア】
北海道潰瘍性大腸炎・クローン病友の会(北海道IBD)
炎症性腸疾患友の会(IBD宮城)
IBDふくしま
【関東エリア】
ちばIBD
埼玉IBDの会
いばらきUCD CLUB
TOKYO・IBD
かながわコロン
かながわCD
【中部エリア】
富山IBD
いしかわIBD結の会
岐阜ちょう会
名古屋IBD
みえIBD
【近畿エリア】
大阪IBD
神戸CD・萌木の会
姫路IBD
【中国・四国エリア】
藍の葉会
【九州・沖縄エリア】
九州IBDフォーラム
九州IBDフォーラム 福岡IBD友の会
九州IBDフォーラム 大分IBD友の会
九州IBDフォーラム 佐賀IBD緑笑会
九州IBDフォーラム 熊本IBD
九州IBDフォーラム IBD宮崎友の会
九州IBDフォーラム チョウチョウ会
九州IBDフォーラム 長崎IBD友の会(ユアジール)
くるめIBD友の会
沖縄IBD
また最近では、同じ病気を持つ人が気軽に集まって話し合える場が徐々に増えてきています。難病や障害の中には見た目ではわからないものも多くあり、他人からなかなか理解されにくいのが現状です。ですが、同じ病気を抱えている人どうしで悩みを分かち合い、また励ましあい支えあうことで、前向きに治療に取り組む原動力にもなります。
〇IBDネットワーク加盟会に公開している患者会
【北海道・東北エリア】
北海道潰瘍性大腸炎・クローン病友の会(北海道IBD)
炎症性腸疾患友の会(IBD宮城)
IBDふくしま
【関東エリア】
ちばIBD
埼玉IBDの会
いばらきUCD CLUB
TOKYO・IBD
かながわコロン
かながわCD
【中部エリア】
富山IBD
いしかわIBD結の会
岐阜ちょう会
名古屋IBD
みえIBD
【近畿エリア】
大阪IBD
神戸CD・萌木の会
姫路IBD
【中国・四国エリア】
藍の葉会
【九州・沖縄エリア】
九州IBDフォーラム
九州IBDフォーラム 福岡IBD友の会
九州IBDフォーラム 大分IBD友の会
九州IBDフォーラム 佐賀IBD緑笑会
九州IBDフォーラム 熊本IBD
九州IBDフォーラム IBD宮崎友の会
九州IBDフォーラム チョウチョウ会
九州IBDフォーラム 長崎IBD友の会(ユアジール)
くるめIBD友の会
沖縄IBD