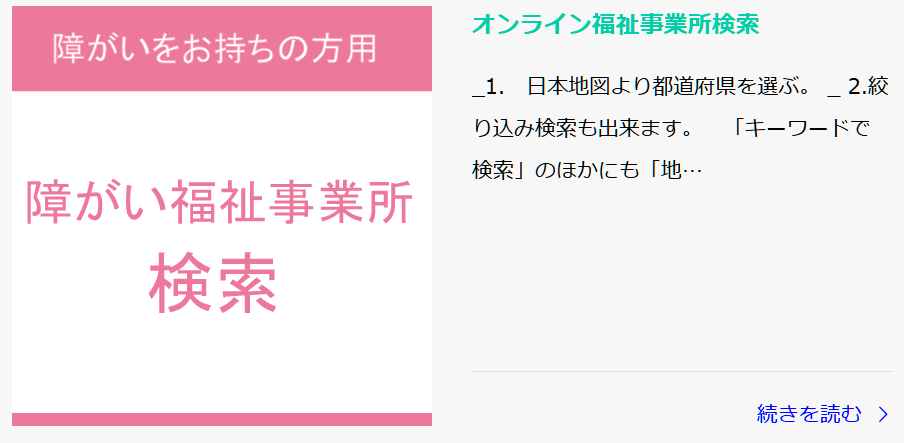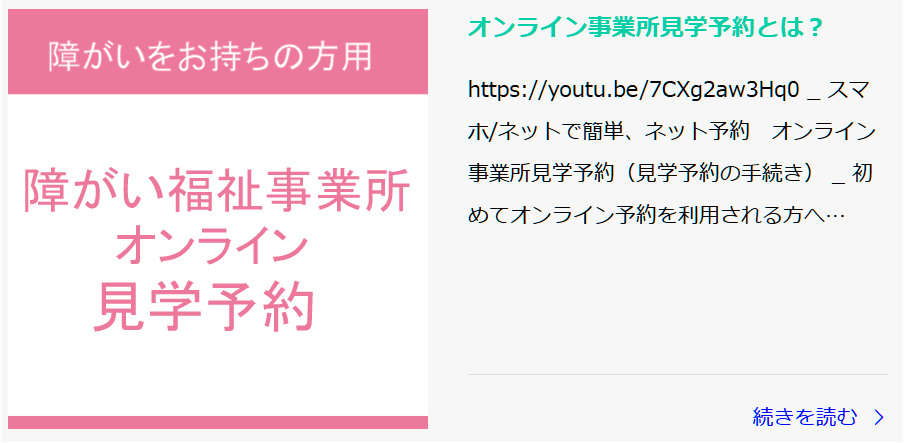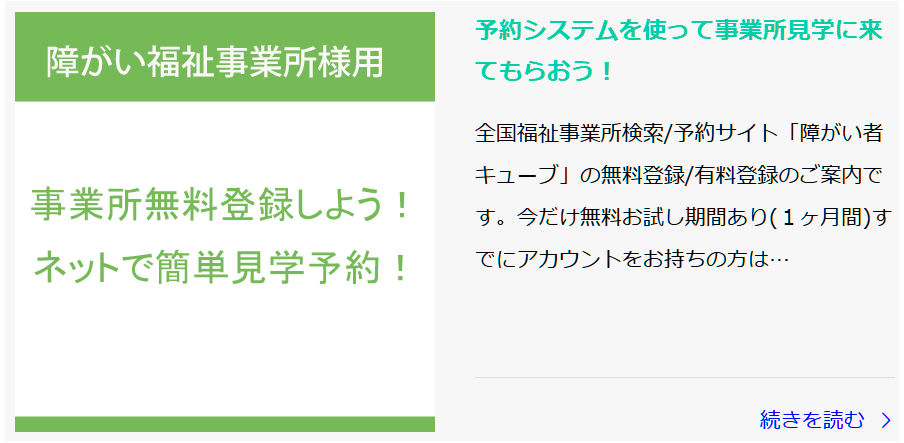・薬の副作用は、だれにでも起こる可能性があります。
医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、一般の方も、医療関係者の方にも、ぜひ知っておいてほしい制度です。
主な副作用の症状と早期発見・早期対応のポイントをまとめた「重篤副作用疾患別対応マニュアル(患者・一般の方向け)」のサイトはこちら
・医薬品副作用被害救済制度の概要
医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」)は、医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献しています。他方、医薬品等は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものであり、副作用の予見可能性には限度があること等の医薬品等のもつ特殊性から、その使用に当たって万全の注意を払ってもなお発生する副作用を完全に防止することは、現在の科学水準をもってしても非常に困難であるとされています。
また、これらの健康被害について、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追及することができても多大な労力と時間を費やさなければなりません。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的として、1980年に創設された制度であり、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度です(再生医療等製品については、2014年11月25日以降より適用)。
・手続きの流れ
- ①給付の請求
健康被害を受けた本人(または遺族)等が、請求書、その他請求に必要な書類(診断書等)をPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に送付することにより、医療費等の給付の請求を行います。給付の種類に応じて、請求の期限や請求に必要な書類等が定められています。 - ②医学・薬学的な判定
PMDAは、給付の請求があった健康被害について、その健康被害が医薬品等の副作用によるものかどうか、医薬品等が適正に使用されたかどうか等の医学・薬学的な判定の申し出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣はPMDAからの判定の申し出に応じ、薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)に意見を聴いて判定することとされています。
迅速な救済を図るため、厚生労働大臣への判定の申し出にあたって、PMDAは、請求内容の事実関係の調査・整理(請求内容の事実関係調査、症例経過概要表の作成、調査報告書の作成等)を行っています。 - ③給付の決定
PMDAは、厚生労働大臣による医学・薬学的判定に基づいて給付の支給の可否を決定します。なお、この決定に対して不服がある者は、支給の決定があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に厚生労働大臣に対して審査を申し立てることができます。 - ④拠出金
医療費等の給付に必要な費用は、医薬品等の製造販売業者等からの拠出金で賄われています。
なお、医薬品副作用被害救済制度に係るPMDAの事務費の二分の一相当額については、国からの補助金により賄っています。
・支給された具体的な事例
- 医療費・医療手当関係
20代女性。インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL接種後、アナフィラキシーを生じて、入院加療を行い、医療費・医療手当が支給された。
40代女性。イブA錠を使用後、多形紅斑型薬疹を生じて入院加療を行い、医療費・医療手当が支給された。 - 障害年金・障害児養育年金関係
50代女性。レボレード錠12.5mg(エルトロンボパグ オラミン)を使用後、肺血栓塞栓症を発症して入院加療を行い、それに続発した低酸素脳症による高次脳機能障害となり、医療費・医療手当・障害年金が支給された。 - 遺族年金・遺族一時金・葬祭料関係
60代男性。イオメロン350注シリンジ135mL(イオメプロール)を使用後、アナフィラキシーショックにより死亡に至り、医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料が支給された。
・給付の種類と給付額
- 入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合 ①医療費 ②医療手当
- 日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合 ③障害年金 ④障害児養育年金
- 死亡した場合 ⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料
給付額は種類ごとに定められております。
なお、それぞれについて請求期限がございますので、ご注意ください。
給付の種類
| 給付の種類 | 説明 |
| 医療費 | 副作用による疾病の治療(注1)に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)を 実費補償するものです(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による)。 |
| 医療手当 | 副作用による疾病の治療(注1)に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです(定額)。 |
| 障害年金 | 副作用により一定程度の障害の状態(注2)にある18歳以上の人の生活補償等を 目的として給付されるものです(定額)。 |
| 障害児養育年金 | 副作用により一定程度の障害の状態(注2)にある18歳未満の人を 養育する人に対して給付されるものです(定額)。 |
| 遺族年金 | 生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を 目的として給付されるものです(定額。最高10年間を限度とする)。 |
| 遺族一時金 | 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、 その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです(定額)。 |
| 葬祭料 | 副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです(定額)。 |
- 注1:医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。
- 注2:障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヵ月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定める1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の対象となります。
《備考》
- 給付の対象となるのは、医薬品等の副作用による疾病に関するものであって、原疾患に関するものではありませんので、ご注意ください。
- 医薬品等の副作用であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能です。
- 「障害年金と障害児養育年金」、「遺族年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。
給付額(2024年4月1日現在 注)
| 給付の種類 | 区分 | 給付額 | |
| 医療費 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 | ||
| 医療手当 | 通院のみの場合 (入院相当程度の通院治療を受けた場合) |
1ヵ月のうち3日以上 | 月額 38,900円 |
| 1ヵ月のうち3日未満 | 月額 36,900円 | ||
| 入院の場合 | 1ヵ月のうち8日以上 | 月額 38,900円 | |
| 1ヵ月のうち8日未満 | 月額 36,900円 | ||
| 入院と通院がある場合 | 月額 38,900円 | ||
| 障害年金 | 1級の場合 | 年額 2,966,400円 (月額 247,200円) |
|
| 2級の場合 | 年額 2,373,600円 (月額 197,800円) |
||
| 遺族年金 | 年金の支払は10年間 (ただし、死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合、 その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、 その期間が7年以上のときは3年間) |
年額 2,594,400円 (月額 216,200円) |
|
| 遺族一時金 | 7,783,200円 | ||
| 葬祭料 | 215,000円 | ||
注:給付額は、給付事由発生月によって異なります。各時期ごとの具体的な給付額については、PMDAにご確認ください。なお、年金(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金)の支給対象期間は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。また、遺族一時金及び葬祭料の給付額は、医薬品の副作用により死亡した方の死亡年月における金額となります。
・制度の手続き方法
給付の請求はご本人などが行います。給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。
請求できる方
給付の種類により、請求できる方が定められています。
| 給付の種類 | 請求できる方 |
| 医療費 | 副作用による疾病の治療を受けた本人 |
| 医療手当 | 副作用による疾病の治療を受けた本人 |
| 障害年金 | 副作用により障害の状態になった本人(18歳以上) |
| 障害児養育年金 | 副作用により障害の状態になった18歳未満の人を養育する人 |
| 遺族年金 | 副作用により死亡した人(生計維持者)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位(注)の人 |
| 遺族一時金 | 副作用により死亡した人(生計維持者以外)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位(注)の人 |
| 葬祭料 | 副作用により死亡した人の葬祭を行った人 |
注:遺族年金(遺族一時金)は、医薬品等の副作用により死亡した人の死亡当時、その人の収入により生計を維持していた(その人と生計を同じくしていた)遺族のうち最優先順位の人に対して支給されます。遺族の優先順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順です(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます)。
なお、同順位の複数の遺族から請求があった場合は、そのいずれに対しても支給決定を行うことになります。各人に支給される額は、遺族年金(遺族一時金)の額を請求人数で除した額となります。
請求に必要な書類
請求に必要な書類は給付の種類によって異なります。以下のとおり、所定の様式での請求が必要となります。
必要な書類は状況によって変わりますので、請求を初めてご検討されている方は、救済制度相談窓口にご連絡ください。
制度の仕組みについてご案内するとともに、状況をお伺いし、PMDAからそれぞれの方に応じて請求に必要な書類をご案内し、お送りいたします。引き続きの請求の場合や、制度について既にご存じの医療機関の方などは、下記の書類をダウンロードしてご使用いただいても構いません。
(注)新型コロナワクチン接種による健康被害について請求をご検討される場合は「医薬品副作用被害救済制度の給付対象」のページをご確認いただくか、救済制度相談窓口にご連絡ください。
留意事項
- 投薬・使用証明書は、副作用救済給付用診断書を作成した医師が投薬した場合(処方せんの交付を含む)は不要です。
- 医療費・医療手当の請求に係る受診証明書は、副作用の治療を受けた病院等で証明を受けることとなります。
- 副作用の治療を受けた病院が2カ所以上の場合は、それぞれの病院等から診断書等を作成していただくことが必要です。
- 複数の給付請求を同時に行う場合、同じ医師による診断書は、副作用のより重篤な症状の様式を使用し、同一の書類の添付は省略して差し支えありません。また、必要な書類を揃えることが難しい場合は、救済制度相談窓口にご連絡ください。
- 電子媒体を提出の場合は、可能な限りCDまたはDVDでの提出をお願いいたします。
- 書類は返却いたしませんのでコピーをお取りください。
- 書類の印刷内容に不備等が生じた場合は、書類をお送りいたしますので、救済制度相談窓口にご連絡ください。